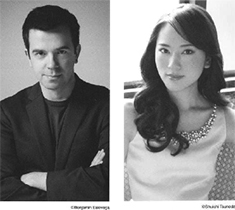CONCERT Review
北村陽&岡原慎也デュオ・コンサート
シューマン:アダージョとアレグロ Op.70
黛敏郎:BUNRAKU(北村陽ソロ)
シューベルト:即興曲集D899から第2番、第3番
ブラームス:チェロソナタ第1番 Op.38
11月6日 藤沢リラホール

家庭的な雰囲気のこじんまりとした演奏会だった。だから聴衆に優しく、温かい気持ちを抱かせたのだろう。シューマンの冒頭、ピアニシモでチェロとピアノの気持ちが一つになっていた。気負いはない、トゲトゲしさもまったくない。それでも大きく広がる。冒頭を聴くだけで、北村・岡原両人が持つ優しく快い空気を感じた。北村は17歳、高校2年生だという。この持って生まれたオーラは確かにそこに存在し、誰にもマネできない、変えられない。しかも、岡原という同じようでいて優しく包み込むオーラを持つ非常にいい共演者を得ていた。生の演奏会から得られるこの安堵感、幸せ感は本当にかけがえのないものだ。2曲目のBUNRAKUを筆者ははじめて聴いた。したがって演奏ではなく作品の方に興味が引かれた。太夫のさまざまに変化する声色や太棹三味線、人形の動きや感情が描かれている。確かに、文楽のさまざまな情景を想起することができ、楽しく聴けた。ただ、ピッチカートがかなり多用され、チェロの弦には負担が多かったのだろう、最後の盛り上がるところで弦が切れてしまった。弦を代えて最終部分から再度演奏された。申し訳なさそうに語った北村の純朴そうな人柄に好感を持った人も多かったのではなかろうか。
シューベルトの即興曲で岡村は、優しい音で真珠が転がるような美しくきらびやかな世界を表現していた。第3番はそれに力強さも加わり、さらに音が流れ続ける無窮動の快さは格別だった。説得力十分だった。そして、最後のブラームス。他では味わえないブラームスだった。岡原はリート伴奏者として名をなしているが、その気配り、そして支えが素晴らしかった。第1楽章ではピアノの音が抑えられている印象を受けたが、それが第2、第3楽章へと進むにしたがい、充実した二重奏に発展した。チェロの高音はあまり印象に残らなかったが、低音の広がりは聴衆を納得させるだけの豊かな音だった。第1楽章ではソナタ形式の形式感も味わわせてくれた。絶対音楽の領袖ブラームスの表現には欠かすことのできない表現力が示されていた。第2楽章のテーマの繰り返しは少し表現に工夫があってもいいのではと思ったが、それでも第3楽章の熱のこもった説得力に時間を忘れ圧倒された。
北村はこれから多くのファンを得るだろう。さらに大きく素晴らしいチェロ奏者に成長することは間違いない。(石多正男)
CONCERT Review
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第346回定期演奏会
ティペット:チャールズ皇太子の誕生日のための組曲
ヴォーン・ウィリアムズ:揚げひばり(ヴァイオリン独奏:南紫音)
シベリウス:交響詩「4つの伝説曲」
指揮:ロリー・マクドナルド
11月12日(金)東京オペラシティ・コンサートホール
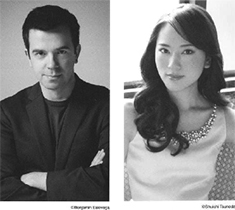
同じヨーロッパでもドイツとフランス、そしてイギリス、それぞれの国民性はかなり違う。筆者はかつてドイツに住んでいたが、イギリスに行くと日本に似たやわらかい優しい雰囲気にほっとしたことを思い出す。この日の演奏ではその思い出がよみがえった。
マクドナルドは東京シティ・フィル初登場とのことだが、指揮のクリアーさ、オケの反応の良さ、そこから導き出される一体感はお互いの新鮮な出会いを楽しんでいるようだった。冒頭、イギリスのティペットの組曲はオケに溶け込むホルンやトランペットがイギリスの田園での快い安らぎを演出していた。行進曲と舞曲からなる第3曲も面白かった。いかにも生まれた子どものお祝いの曲だった。次の「揚げひばり」もイギリスの作曲家のヴォーン・ウィリアムズによるもので、ヴァイオリン独奏が活躍する。南はイギリスの風景、空気感を見事に描き出していた。冒頭、静けさの中からひばりが舞い上がる様子はターナーなどのイギリス絵画を見るようだった。音が澄んでいてきれい。力で圧倒するのではなく、聴かせる音楽を奏でていた。繊細さがこれほど快いとは。素晴らしかった。最後のシベリウス「4つの伝説曲」は自由奔放で向こう見ず、また好色な若者を描いた作品で、4つの交響詩で構成されている。シベリウスはフィンランドの作曲家だが、イギリスの演奏家も好んで演奏する。第1曲は乙女たちとの色事と強奪を描いているが、大太鼓と弦の表現に圧倒された。第2曲は有名な「トゥオネラの白鳥」。ここではイングリッシュ・ホルンとチェロに聞き惚れた。第3曲は若者の死を描く悲劇的な曲想を持つ。弦のトレモロとクレッシェンドに説得された。そして第4曲。ここでは生き返った若者が描かれる。エネルギッシュで華やか、まさにマクドナルドと東京シティ・フィルの熱演だった。イギリス的優しさに迫力が加わり興奮させられた。
帰路に着くとき、あらためて自分が優しい気持ちになっていることを感じた。素敵な演奏会だった。(石多正男)
CONCERT Review
ミヒャエル・ハイドン・プロジェクト
#03 『ヴェルグルのバス弾き』酒に溺れた男の音楽劇
ミヒャエル・ハイドン(1737~1806)
●ディヴェルティメント 変ホ長調 MH.9より第1楽章
●シンフォニア ト長調 (APPLAUSUS “Quid video superi?” MH.144よりSinfonia Allegro molto かつ CANTATA ”Der gute Hirt” MH.181より Introduzione)
●1幕からなる音楽劇≪ヴェルグルのバス弾き≫MH.205
総監督:布施砂丘彦
演出/照明:植村 真
ドラマトゥルク/翻訳/字幕:相馬 巧
美術:小駒 豪
リーズル(妻):澤江衣里(ソプラノ)
バートル(夫・バス弾き):渡辺祐介(バス)
助演:神田初音ファレル(ダンサー・俳優)
Vn.:原田 陽/大光嘉理人 Va.:伴野 剛 Vc.:上村文乃 Cb.:布施砂丘彦 Cem.:星野友紀
2021年11月19日 北千住BUoY

2021年コロナ禍に、「ミヒャエル・ハイドン・プロジェクト」が立ち上げられた。主催代表は、コントラバス奏者の布施砂丘彦。忘れられた作曲者にスポットを当て、その音楽を広める。これがコンセプトの音楽団体である。全5回。9月から毎月1回の形で演奏会とレクチャーを企画し、これまでミヒャエル・ハイドンが不当な扱いを受けたとして再評価に挑む。
第3回の日本初演のオペラ「ヴェルグルのバス弾き」MH.205を観た。ほかの回は「近江楽堂」(東京オペラシティ)などで、なぜ当回のみ滅多に足を運ぶことのない不慣れな北千住の地かと、いぶかしく思ったのも正直なところ。ここに最初の仕掛けがあった。
駅からの往路、道案内のスマホ画面に目が釘付けのままホールにたどり着き、辺りを見落とした。だが、音楽が始まるとすぐ意味が解ける。終演後には、暗くなり駅前の飲み屋街の灯りを通り抜けながら、先ほどまでの飲んだくれの物語が身に沁みる。今度は独り笑いして、なかなかの知恵者集団と見た。
プログラムの主宰者の言葉によれば、会場BUoYは「元銭湯の廃墟」という。そこに作られた打ちっぱなしのコンクリートのアートスペースで、「ピリオド奏法」と「現代演出」のオペラ上演。「一見矛盾する組み合わせで上演したかった」とのこと。この公演で確かに、“もう一人のハイドン”のイメージが頭に刷り込まれたのは間違いない。
フロアーを大きく3つに区分し、左端がバーカウンター。ホールに最初に入った時には、ここで本当にアルコールが飲めるのかと思った。幸い自分は下戸なので座らなくてよかったが。そして中央の大きな間取りに、奥に楽器奏者、その前の空間と、衝立のように設えられた扉から右側の、マイホーム風の空間が舞台。
メインの1幕オペラは20分ほどの作品である。その前のディベルティメントとシンフォニアからすでに前座が始まる。というのも通奏低音の流れる中、ヴィオラとチェロが掛け合うリズムをうまく捉えて、左のバーカウンターで“客とマスター”の寸劇が始まる。シンフォニアに入るころには、“客”はアルコールが回って千鳥足。この“客”がオペラの主役バートルになる運び。
ヨーゼフ・ハイドンの弟、ザルツブルク宮廷音楽家ミヒャエル・ハイドンがディヴェルティメントやシンフォニアを作るとき、まさか酒に溺れた様を音にしたはずはないだろう。しかし楽器が相互に掛け合うリズムや、強弱の推移を音に聴くと、さもありなんと思えてくるから不思議。
音楽喜劇が始まると、バートル役・渡辺祐介のバスの、酒に溺れた様は絶好調。一方、ソプラノの澤江衣里は、飲んだくれ夫の妻の心境がいつの世も変わらぬ核心をつく。だが物語は、バートルによる妻との駆け引き芝居で立場が逆転する。一時代前ならまだしも、ジェンダーの喧しい昨今。21世紀にこのオペラは生き残れるか、ミヒャエル・ハイドン復権は果たしてなしうるか、かえって気掛かりになる。
とはいえ、字幕、ならびにプログラムに挟まれた歌詞対訳(訳:相馬巧)は註も添えられ、貴重な資料となった。文化庁の助成を受け、音楽雑誌の協力も得ての公演。フリーランスの若い芸術家たちが工夫を凝らし、埋もれた作品を音にしたプロジェクトの意義は、コロナ禍を見据えると計り知れない。(宮沢昭男)
写真:(c)岡田直己