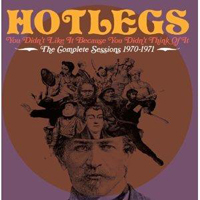|
ミュージック・ペンクラブ・セミナー・リポート
第1回「私だけが知る素顔のザ・ビートルズ」・・・・・講師:星加ルミ子 11月16日 パイオニア・プラザ銀座 |
 記念すべき第1回MPCJセミナーは、日本でビートルズと言えばこの方、星加ルミ子さんを講師にお招きし、「私だけが知る素顔のザ・ビートルズ」と題して1時間30分の大変有意義な時間を過ごした。 記念すべき第1回MPCJセミナーは、日本でビートルズと言えばこの方、星加ルミ子さんを講師にお招きし、「私だけが知る素顔のザ・ビートルズ」と題して1時間30分の大変有意義な時間を過ごした。ビートルズのデビュー50周年に当たる今年、星加さんは全国で引っ張りだこの大人気で大忙しだ。 ビートルズへの単独インタビューに初めて成功し、その後もメンバーと親しく交流を続けた星加さんならではの話を聞く事が出来るとあって、会場は平日にもかかわらず満員御礼となり、セミナー形式の内容としては、最高の申し込みとなった。 さて本題であるが、ビートルズが62年にデビューした後、アメリカに乗り込み大ヒットしていた頃、日本国内では当時の東芝EMIの担当者が業界関係者へテスト盤を持って回っていたそうだが、星加さんにとってロックンロールは、アメリカの音楽であり、イギリスのぽっと出のバンドが長続きする訳がないと思ったそうだ。(こう言う事を正直に話す所が、星加さんの素晴らしい所であり、多くの方に好かれる要因でもある) そんな星加さんをビートルズに目覚めさせてくれたのは、何を隠そう当時の飛んでる女子高生達だったという。 熱狂的なビートルズ・ファンの彼女達の勢いに負け、ビートルズを真剣に聴くことから始め、その良さに気付いた時には、彼らに会いに行こうと思ったそうだ。 当時(1$=360円)、パスポートも簡単に取得出来ず、何かと制限が多かった時代に、面会のOKも出ないまま、イギリスへ旅立った星加さんのど根性が凄い!!!行けば何とかなると思ったそうだ。(20年後に、私も最初の出張がイギリスだったが、こんな根性はなかった。本当に尊敬に値する) マネージャーのブライアン・エプスタインにどうしてもOKを貰う為に用意したお土産は、今では絶対にあり得ないXXXだったのだ。(XXXは、ご想像下さい) 勿論、名のあるXXXであり本物だ。 このアイデアは、当時全世界で大ヒットしていた黒澤明の映画「七人の侍」からヒントを得たと言う。 加えて、何かあったら不味いので(何かあったらおしまいの様な気がするが)イミテーションのXXXを4本用意し、合計5本のXXXを袋に入れて、飛行機の機内に持ち込んだそうだ。(狂気の沙汰?) まさか可愛い日本女性がXXXを5本も持って搭乗しているとは、誰も考えなかった様だ。(奇跡!!!)  先ず、ビートルズのメンバーがデビュー前に修業したドイツ・ハンブルグで女の子達に取材し、パリでカメラマンと通訳に合流し、いざロンドンへ出発した。 先ず、ビートルズのメンバーがデビュー前に修業したドイツ・ハンブルグで女の子達に取材し、パリでカメラマンと通訳に合流し、いざロンドンへ出発した。ビートルズに会う為に、ありとあらゆる努力をし、機が熟したと感じた時にマネージャーへXXXをプレゼントし、インタビューのOKを貰ったのだ。 素晴らしい行動力と判断力である。 アルバム『HELP』のレコーディングが終了した瞬間の30分間が、与えられたインタビューの予定であったが、ビートルズの4人が星加さんを気に入り、インタビューの内容は全て各人が記入してくれ、雑談が3時間にも及んだ。 悪ぶる所が一切なく、気さくに話をしてくれる4人に好感を持った星加さんに対し、4人も初めて話をする日本女性に興味を持ったのだろう。 ポールは、フロントマンとして気持ち良く話をし、メンバーに仕事を割り振り、雰囲気を和らげてくれ、はにかみ屋のジョンは、星加さんと意気投合した後は、元々日本に興味があった様で、相撲レスラーのことなど星加さんが答えられない事までも聞いてきた。 ギター小僧のジョージは、ポールとジョンの陰に隠れ、リンゴは自分が最後にメンバーになった者として立場をわきまえていた。 着物姿の星加さんを囲んだ4人の写真が、ミュージック・ライフの表紙を飾り、誰もインタビュー出来なかったビートルズの真実が掲載され、瞬く間に日本全国にビートルズ・ファンを増やしていった。 星加さんは、この記念すべきインタビュー記事を自分で持ち変えることはなく、日航のステュワーデスさんに託したそうです。(残ってビートルズ以外の取材もする様に会社から命令があったそうだ) こうしてビートルズと星加さんの友情は始まり、ビートルズがアメリカでライヴをやるとなれば呼ばれ、日本武道館のライヴでもバックステージに呼ばれ、ロンドンでレコーディングがあると呼ばれ、ラストとなったルーフ・ライヴの時にもアップル社の1階に星加さんは居て、ライヴ終了後ポールと簡単な挨拶をしただけで、ビートルズとの関係は終了した。 星加さんの思い出として、『マジカル・ミステリー・ツアー』のレコーディングの取材の時初めてオノ・ヨーコさんに会った事、「フール・オン・ザ・ヒル」のフールとは賢者であって、おバカさんではない事をポールから教えてもらい、ポールが間奏のメロディをピアノで弾いている時、リコーダーが良いんじゃないかとジョンが言うと、瞬間的にリコーダーが出て来るというビートルズならではのエピソードを語ってくれた。 レコーディングの最中、プロデューサーのジョージ・マーティンは一切彼らに指示をしないで、好きにやらせていたそうだ。 ジョージ・マーティンを加えた5人が、本当にアイデアの宝庫だった。 1時間30分という限られた時間の中で、星加さんは本当に印象的な話を大忙しで話された。 まだ話し足りない様子なので、いつの日か時間が経過し、話が出来るようになった内容も含め、心行くまで大いに語って頂こう。 この日は、ビートルズ・ファンいや音楽ファンにとって、至福の時を過ごすことが出来たことは間違いない。 星加ルミ子という本当に小柄な女性が、誰も成しえなかった大きな歴史を築いた事を音楽ファンは決して忘れないだろう。(絶対に忘れてはいけない)(上田和秀) 撮影:池野 徹 |
|
「アンサンブル インタラクティヴ トキオ(EIT)コンサート」
11月2日 府中の森芸術劇場 ウィーンホール・・・・・・・三橋圭介 |
| 2005年に湯浅譲二と韓国の国際的な作曲家である姜碩熙を顧問に迎えて結成されたアンサンブル・インタラクティブ・トキオの公演をきいた。プログラムは姜碩熙とサンゴン・ファンの世界初演作品に加え、ユキ・モリモト、ジグムント・クラウゼ、湯浅譲二の6作品で、ソリスト集団としての「インタラクティブ」な特性を生かし、デュオから室内オーケストラ編成まで作品が取り上げられている。指揮は森本 恭正(ユキ・モリモト)。 姜碩熙の作品はタイプの異なる2曲で、最初はフルートとバスクラリネットのための即興曲(1994)。2つの楽器の細かい動きとユニゾンとの掛け合いが形を変えていく。即興的な赴きだが、計算された持続を持っている。世界初演の室内オーケストラ作品「オクタゴン」は、多層的な色彩のリズムが多様に繰り出されていく。それぞれの音は調性的ではないが、協和的な戯れのなかで蠢いている。この作曲家ならではの空間造形が聴かれた優れた作品で、複雑な響きを指揮の森本が巧みにまとめていた。サイゴン・フアンによる世界初演作「ウィンボ ディプロス」は、ジャズのラグタイムからベートーヴェンなどが織り込まれたノリの良いポストモダン。ポップからシリアスまでを縦横無尽に渡り歩く。演奏も見事だ。 後半のモリモトの日本初演作「トレデキム」(2010)は、冒頭の弦の震えとピアノと打楽器のしなだれ落ちるようなリズム・パターンにさまざまに楽器が絡み、リズムを保持しながら変容を繰り返し、倦怠感と官能的なエロスの香りを彩っていく。それはウィーン世紀末的な残り香のようでもあり、そこで長らく生きてきたモリモトの血肉の新たな発酵が感じられた。クラウゼのクラリネット、トロンボーン、チェロとピアノのための「ポリクロミー」(1968)は、初期の代表作のひとつといってもいいかもしれない。伝統的な意味での緊張やクライマックスをもたないユニスティック・ミュージックであり、微妙な楽器の色彩が限られた音で浮遊し、戯れる。湯浅の弦楽トリオのための「プロジェクション」(2001)は、強い表出力をもった作品で、同じような音の身振りをもった3つの楽器が付かず離れずの関係で色彩を滲ませていく。その滲み具合の振れ幅が独特な作品だ。 全体に作品、演奏の質も高く、とても興味深い演奏会だが、ひとつ感じることは若手の邦人作曲家の作品がないことだろうか。今後、若い人に門を開いたインタラクティブなコンサートを期待したい。 (この批評は当日の録音に基いて書いた。) |
|
「日生劇場開場50周年記念〈特別公演〉読売日本交響楽団創立50周年記念事業 二期会創立60周年記念公演オペラ《メデア》」 11月10日 日生劇場・・・・・・・・・・・・・・藤村 貴彦
|
| 「メデア」はギリシャ悲劇を読んだ人ならだれでも知っているであろう。夫イアソンがほかの女と結婚する事を知り、その復讐に彼との間に産んだ二人の子を殺す戯曲。作曲者のライマンは、オーストリアの文豪グリルパルツァーの戯曲「金羊皮」を基に自ら台本を記し、2010年ウィーン国立歌劇場で初演され、絶賛されたという。現代オペラの上演は、ヨーロッパでは日常的に普通に行われているが、日本での初演になると、実験とか力みのような雰囲気が伴ないがちである。今回の公演では周到な準備を重ねて、広くオペラ愛好家の日常の楽しみに供するような出来具合のように思われ、全曲を息つく暇もなく聴き通す事が出来た 。その事を高く評価したい。 いやはや、それにしてもライマンの音楽は凄まじい。日本のオペラ作曲家にはなかなか見られない緊張感、持続力があって、ワグナー、ベルクの延長線上にこのオペラがあるような気がした。金管の持続音の強奏、そして弦楽器群の特殊奏法などが、声楽パートとからみ、それらが基本的には、暗欝とした音色で平行的に進んでいく。いつも同じような響きのように思われるが、歌とオーケストラの連携は、複雑な形を示しているのだろう。一度聞いただけでは理解できなかったというのが正直な感想である。  金羊皮などを地中深く埋めようとするメデア=大隅智佳子 金羊皮などを地中深く埋めようとするメデア=大隅智佳子声楽パートも極度に難しく書かれており、メリスマ的な技巧と、広い音域の跳躍が用いられ、日本人の声楽界に蓄積された力は、今やこの段階にまで達したのかと改めて感心しながら聞いた。筆者が聞いたメデア役の大隅智佳子、イアソン役の与那城敬は正確な技術とゆとりのある内面的な表現で歌いあげていたと思う。他の声楽陣も今回の公演のために懸命に努力した跡がみられ、さすがに優秀な人材をそろえている二期会である。 飯塚励生の演出も良かった。簡素に作られた舞台で、舞台上に軽重両面を描き分けていて、振付の大畑浩恵のダンサーの動きが、ギリシャ悲劇で重要な役目を果たすコロスを演じていたように感じられた。ダンサーの踊りを取り入れた最近のオペラ演出が多いなかで、メデアはダンサーが効果をうまく引き立てており、これぐらいの動きがちょうどよい。  メデアに嫌気が差し始めているイヤソン=与那城敬 メデアに嫌気が差し始めているイヤソン=与那城敬下野達也の指揮は、歌手とオーケストラを完全に把握し、けじめのはっきりとしたベテランの棒であった。下野の新作作品にかける情熱が聴き手にも伝わってくる。現代オペラの上演と言うと、聴衆の動員、費用などを心配して、めったに演奏される機会は少ない。今回は三つの団体が協力しあっての公演であったが、新作オペラの上演は、新たな音楽文化の地平を切り開いてゆく。勇気を持ってこのような企画を継続してもらいたい。来年はライマンのオペラ「リア」が上演されると言う。楽しみである。 (写真撮影:三枝近志) |
|
武満徹の音楽シリーズ 第3回「遠い呼び声の彼方へ」
11月23日 文京シビックホール(大ホール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤村貴彦 |
 武満徹が亡くなってから6年過ぎたが、彼の作品はしばしばオーケストラで演奏され、今年の11月にはNHK交響楽団で、「遠い呼び声の彼方へ」、「ノスタルジア」が取り上げられた。12月は「ノヴェンバー・ステップス」である。忘れ去られてゆく事が多い日本の作曲家の中で、何故、武満の音楽が数多く演奏されるのであろうか。武満の音楽の特徴は、初期から変わることのない聴覚的イメージ、聴覚的想像力の占めている役割が大きく、そこには聴衆に対して押しつけがましい所がない。武満の音楽の魅力であり、その事が演奏される理由だと思う。 武満徹が亡くなってから6年過ぎたが、彼の作品はしばしばオーケストラで演奏され、今年の11月にはNHK交響楽団で、「遠い呼び声の彼方へ」、「ノスタルジア」が取り上げられた。12月は「ノヴェンバー・ステップス」である。忘れ去られてゆく事が多い日本の作曲家の中で、何故、武満の音楽が数多く演奏されるのであろうか。武満の音楽の特徴は、初期から変わることのない聴覚的イメージ、聴覚的想像力の占めている役割が大きく、そこには聴衆に対して押しつけがましい所がない。武満の音楽の魅力であり、その事が演奏される理由だと思う。人は武満の音楽の事を、墨絵のようであり、あの空間の広がりを武満が求めた世界だという。私は武満の音楽を聴いていると、印象派の画家、マネ、モネの絵が眼前に浮かぶようで、光、波、風という自然界の様々な現象をイメージする。印象派の絵画は色彩を重視する。色彩を音色に例えるならば、武満のオーケストラ音楽は、音色の微妙な混合、微妙な変化であり、色彩的なオーケストラの蓄積によって、全体が形作られる。 「武満徹の音楽」第3回は彼のオーケストラ作品を年代順に聴くもので、「弦楽のためのレクイエム、「樹の曲」、「地平線のドーリア」、「アステリズム」、「冬」、「遠い呼び声の彼方へ」、6曲のオーケストラ曲と、ピアノ・ソロ「フォーアウェイ」、「閉じた眼」、それにヴァイオリンとピアノの「十一月の霧と菊の彼方」が演奏された。一曲、一曲については改めて紹介する必要はないだろう。既に何度も演奏されているからである。コンサートでは「冬」が、絵画的な作品であり、美しい雪の高原の中に、素粒子が空中に飛び散り、陽の光を受けて七色の虹が現れ、妖精と戯れているような感じで、武満の特徴が最もよく表現されていた。指揮者は高関健。音楽の一区切りが大変きちんとできており、 音色の作り方も巧みであった。こまやかな表情も念入りに磨かれていて、全6曲を飽きさせないで聴き手に伝える高関の手腕を高く評価したい。 「アステリズム」とピアノ・ソロを弾いた高橋悠治も、音楽の内に深く入った演奏で、響きが美しかった。 ヴァイオリニストの漆原啓子はどのフレーズにもきわめて鋭敏で、かつ繊細な神経が行き届いた表現。 武満の音楽は古典の中に入ろうとしている。その事を実感したコンサートであった。聴衆の入りを心配したが来場者も多く、さすが文化の質が高い文京区である。日本の各地には立派なコンサートホールがあり、それぞれが独自の催しを行っているが、相変わらず名の知られた演奏家を招聘し、創造的なコンサートは少ない。日本の作曲家の作品による催しは非常に重要であり、音楽文化の貢献はまさにそこにある。 文京区に在住し、音楽の拙な文章を記して、それで生計を営んできた私には、今回の企画は大変うれしく、そして誇りでもあった。このようなコンサートの灯を消さないで、継続していってもらいたい。 (写真提供:Schott Music Archive) |
|
やっぱりバーブラは最高「バーブラ・ストライサンド/バック・トゥ・ブルックリン」
(10月29日 カナダ バンクーバー ロジャース・アリーナ)・・・・鈴木道子 |
 バーブラ・ストライサンドは、アメリカのショウ・ビジネス界きってのスーパースターだ。歌手・映画・ミュージカル女優・映画製作者・監督etc.。受賞もグラミー賞・トニー賞・エミー賞・アカデミー賞・ゴールデングローブ賞・その他諸々。環境保護や女性のリーダーとしても尊敬されている。まさに掛け替えのないトップに君臨して半世紀となる。彼女は60年代からの新旧未発表曲を集めた最新盤『リリース・ミー』を出したばかりだが、6年振りのコンサート・ツアーを行った。タイトルは『バック・トゥ・ブルックリン』。彼女の生い立ちの地へ想いを馳せたコンサートだ。1964年のセントラル・パーク・コンサート以来、僅か88回しかコンサートをやっていないというし、彼女ももう70歳。そうそうコンサートをやるとも思えないので、カナダはバンクーバーのロジャース・アリーナへ出かけて行った。(10月29日) バーブラ・ストライサンドは、アメリカのショウ・ビジネス界きってのスーパースターだ。歌手・映画・ミュージカル女優・映画製作者・監督etc.。受賞もグラミー賞・トニー賞・エミー賞・アカデミー賞・ゴールデングローブ賞・その他諸々。環境保護や女性のリーダーとしても尊敬されている。まさに掛け替えのないトップに君臨して半世紀となる。彼女は60年代からの新旧未発表曲を集めた最新盤『リリース・ミー』を出したばかりだが、6年振りのコンサート・ツアーを行った。タイトルは『バック・トゥ・ブルックリン』。彼女の生い立ちの地へ想いを馳せたコンサートだ。1964年のセントラル・パーク・コンサート以来、僅か88回しかコンサートをやっていないというし、彼女ももう70歳。そうそうコンサートをやるとも思えないので、カナダはバンクーバーのロジャース・アリーナへ出かけて行った。(10月29日)彼女にとって初めてコンサートを行う都市だ。19,000人収容の会場はほぼ満員ながら、当地の意識はニューヨークほどには熱くない。バーブラを評するのに、地元紙の告知によると「ヴェテラン・パフォーマー」だって。周りはドレスアップしたバンクーバーのセレブ達。ジャズ・ピアニスト・シンガーのダイアナ・クラールもきていた。1,2階席は若者も少なくないが、アリーナやステージ近くの観客はチケットが500ドルと高いので、50、60代中心の男女とみた。両隣は共に娘連れの熱狂的なファンとのことだった。「アルバムは全部持っているの」。 彼女の初主演ミュージカル『ファニー・ガール』のメドレーによるフルオーケストラ(ビル・ロス指揮)演奏に次いで「ユール・ネヴァー・ノウ」でバーブラ登場。皆拍手とスタンディング・オヴェイションで迎える。この曲は彼女がプロ・デビューする以前に自主録音した初レコーディングの曲だ。6年前の公演より十分シェイプアップして、黒いドレスからも魅力的な脚が見える。容姿も衰えず、何よりも美しい声が素晴らしくよく出ていた。 「ある晴れた日に永遠が見える」に次いでジャジーな「ナイス・ン・イージー/ザット・フェイス」「ビウィッチト」、そして『リリース・ミー』からのジム・ウェッブ作品「ディドント・ウィ」などの後、一組目のゲスト、イタリアの少年3人組イル・ヴォロが登場する。TV番組「アメリカン・アイドル」で昨年人気爆発した17歳から20歳の3人組は、イル・ディーヴォのようなオペラティックな美声の持ち主だが、より自然でなかなかの歌手たち。6年前のライヴにゲスト出演したイル・ディーヴォよりずっとよかった。「スマイル」ではバーブラも加わる。「ウン・アモーレ・コシ・グランデ」「オー・ソレ・ミオ」を精一杯歌って大きな拍手をもらった。 バーブラがファンからの質問状を読むセグメントでは笑いを誘い、ご当地ブライアン・アダムスの話から「ファイナリー・ファウンド・サムワン」を軽く歌う。今年5月に亡くなったドナ・サマーを偲び「イナフ・イズ・イナフ」。続いてこの8月に亡くなった親しい友人マーヴィン・ハムリッシュを偲ぶコーナーでは、思い出を語りながら、彼の作曲による「追憶」をレコードよりもドラマチックに素晴らしく美しく歌って感動を呼ぶ。メドレーで映画『アイス・キャッスル』のテーマ「スルー・ザ・アイズ・オブ・ラヴ」も加わる。またバーブラが初主演『ファニー・ガール』以来親しいもう一人ジュール・スタインの作品集を歌うシーンでは、『リリース・ミー』の冒頭に入っていた「ビーイング・グッド・イズント・グッド・イナフ」、ミュージカル『ジプシー』から「ローズ・ターン」「サム・ピープル」、『ファニー・ガール』の「パレードに雨は降らせないで」など説得力、迫力と演劇的なおもしろさも加えて歌い、圧巻の前半を終えて20分間の休憩となった。 第2部は、ブルックリン時代の映像がふんだんに投影される。バーブラはオレンジ色のドレスに着替え、「マイ・マン」。次いで人気トランペッターのクリス・ボッティを迎え、彼の活躍も目覚ましい。一緒にファンタスティックな「ホワットル・アイ・ドゥ」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」を。次いで『スター誕生』からの「愛に迷って」「スター誕生の愛のテーマ」が、のびやかで素晴らしく美しい。どこか幻想的でありながら存在感のある演唱は見事で、当夜のハイライトの一つとなった。 デヴィッド・フォスターが支援する美女ヴァイオリニスト、キャロライン・キャンベルとクリスの「エマニュエル」他もいいアクセントとなった。クリスはドラムスをフィーチャーした「恋した時に」も熱演する。そうした間にバーブラはしばしの休憩をとり、再度登場。スクリーンにはバーブラの誕生祝い(4月24日)にと一人息子で俳優のジェイソン・グールドが制作した母子の思い出のフィルムが映しだされ、微笑ましくなる。バックでゆったりと流れる「ネイチャー・ボーイ」がよかったが、これがジェイソン本人だとは。滑らかでうまいのに驚いた。その後も「愛は海よりも」を母子デュエット。彼のソロでアメリカ大統領選に絡んで「マスカレード」などを歌ったが、バーブラの特訓がきいた(?)好唱は魅力的で、歌手としても今後が楽しみになる。 いよいよエンディングとなり、優美な「ピープル」「ヒアズ・トゥ・ライフ」がファンを魅了する。「満足はしてるけれど、でも未だハングリーよ」と語る彼女の言葉は、いかにもバーブラらしい。クリスの吹く『キャンディド』に促されるように、当夜のゲスト総出演。大コーラス隊も加わって、「メイク・アワ・ガーデン・グロウ」「サムホエア」でバーブラは一旦ステージを降りた。そしてアンコール。妹で歌手のロスリン・カインドを伴い、二人で「幸せの日々はここに再び/ゲット・ハッピー」をデュエット。「サム・アザー・タイム」を優美に歌って、2時間半に及ぶステージをスタンディング・オヴェイションで終了した。 バーブラのコンサートは過去に3回観ているが、今回ほど気負いなく、悠々と自然体で進行したことはなかった。また、美しい表現の歌は従来より演劇的な要素が蒔かれたのは珍しい。これも『バック・トゥ・ブルックリン』のせいかも知れない。かつては非常に個性的な演劇性で注目されたバーブラだった。70歳となっても衰えないどころか、現役ばりばりのスーパースターに、大きなエールを送りたい。 撮影:Firooz Zahedi |
|
「ザ・ローリング・ストーンズ」の真実が迫る。
50周年ドキュメンタリー映画"Cross Fire Hurricane"。・・・・・・・池野 徹 |
 ロックグループとしては50年を経た、希有のストーンズがいよいよ動き出した。ロンドンO2アリーナで11/25,29のコンサート。ニューヨーク・プルーデンシャル・センターで12/13,15のコンサート等が行われるニュースが世界を走った。そんな中で11月7日、ザ・ローリング・ストーンズ結成50周年記念公式ドキュメンタリー映画のジャパンプレミアが、Zepp Diver City Tokyoであった。タイトルが"The Rolling Stones-Cross Fire Hurricane"で、何がと思わせるが、よくある過去の時代の集大成の記録映画と思ったら、とんでもない映画だった。映画のEx Producerにマーティン・スコセッシが監修しており、監督は若手のブレット・モーゲンは、ストーンズのヒストリーを、残された時代の数千時間のナマのフィルム、数万枚のスチルフォト、数十曲の未テイクを含む音源から抽出してエディティングした作品となっている。 ロックグループとしては50年を経た、希有のストーンズがいよいよ動き出した。ロンドンO2アリーナで11/25,29のコンサート。ニューヨーク・プルーデンシャル・センターで12/13,15のコンサート等が行われるニュースが世界を走った。そんな中で11月7日、ザ・ローリング・ストーンズ結成50周年記念公式ドキュメンタリー映画のジャパンプレミアが、Zepp Diver City Tokyoであった。タイトルが"The Rolling Stones-Cross Fire Hurricane"で、何がと思わせるが、よくある過去の時代の集大成の記録映画と思ったら、とんでもない映画だった。映画のEx Producerにマーティン・スコセッシが監修しており、監督は若手のブレット・モーゲンは、ストーンズのヒストリーを、残された時代の数千時間のナマのフィルム、数万枚のスチルフォト、数十曲の未テイクを含む音源から抽出してエディティングした作品となっている。1962年、ローリング・ストーンズとして結成。1963年、シングル「Come On」でデビュー、1964年、アルバム「The Rolling Stones」を発売して全米デビューする。同時期にビートルズがスタートして1963年「Please Please Me」がビッグヒット。それに対抗したストーンズは、「悪」のイメージを戦略的に打ち出す。そのターゲットが時代の流れにはまり走り出す。1967年、ミック・ジャガーとキース・リチャードが大麻所持で有罪判決を受ける。ドラッグとの格闘が始まる。1969年、ブライアン・ジョーンズが脱退急逝、ハイドパークでのフリーコンサート、そして、オルタモントの悲劇が起きる。 激動の60年代であった。そして、ベロマークが設定されローリング・ストーンズレコードが発足。1976年ミック・テイラーの脱退、そして、ロン・ウッドの加入、1978年シングル「Miss You」が大ヒット、70年代も話題豊富のストーンズであった。この60,70年代の時期にストーンズの楽曲の全てが出来上がったと言って良い。この間のストーンズの生き様が見事に映画は捉えてる。ストーンズのメンバーが振り返る当時のナレーションが効果的にドキュメント性を高めてる。次から次に繰り出すヒット曲とミックをはじめそのパフォーマンスは、たたみ込んで迫って来る。 時代に仕掛けられたストーンズが、仕掛けに応えたストーンズが、仕掛けに乗った観衆と、仕掛けるメディア、そして、その時代に見事乗り切ったストーンズの生き様が、ヒット曲にマッチングして、若々しく、荒々しい、ストーンズの魅力を真実を、圧倒的に見せる映画になってる。ロックンローラーの「悪」の生き様を、現在まで生きて来た証をストーンズは演じてる。 ストーンズメンバーそれぞれの話題豊富な女性関係が、全く姿を見せないのを終わって気がついた程である。人間的パフォーマンスより、音楽的、社会現象的事実を強調したかったのだろう。映画の冒頭レッドカーペットを歩く50年を経たストーンズの面々は、21世紀にもカッコ良く生きてるのを確認できたのは印象的だった。 昨今、大仕掛けの造り物、CG過剰の映像時代に、ナマの映像記録だけで人間を浮かび上がらせたエンターテインメント作品として、ストーンズを知るもの、知らないもの、若きミュージッシャンにぜひ見て欲しいと思った。 しかし「ワル」のストーンズがいちばん輝いてるよね。 |
|
ミュージカル「The Fantasticks(ファンタスティックス)」博品館劇場 11月7日・・・本田浩子
|
 世界のロング・ラン・ヒット・ミュージカルといえば、今の若者なら「オペラ座の怪人」、「レ・ミゼラブル」或いは「キャッツ」を思い浮かべるかもしれないが、そうではない。脚本と詩をトム・ジョーンズ、音楽をハーヴェイ・シュミットで1960年にニューヨーク市のグリニッチ・ヴィレッジの小さな劇場で幕を開けたオフ・ブロードウェイ・ミュージカル「ファンタスティックス」は、Try to Remember (思い出そう)という名曲と共に、まさに42年間という最長上演を誇る永遠のミュージカルであり、今なお世界中で上演されている。 世界のロング・ラン・ヒット・ミュージカルといえば、今の若者なら「オペラ座の怪人」、「レ・ミゼラブル」或いは「キャッツ」を思い浮かべるかもしれないが、そうではない。脚本と詩をトム・ジョーンズ、音楽をハーヴェイ・シュミットで1960年にニューヨーク市のグリニッチ・ヴィレッジの小さな劇場で幕を開けたオフ・ブロードウェイ・ミュージカル「ファンタスティックス」は、Try to Remember (思い出そう)という名曲と共に、まさに42年間という最長上演を誇る永遠のミュージカルであり、今なお世界中で上演されている。 ニューヨークに行けば、今ではグリニッチではなく、ブロードウェイの50丁目、タイムズ・スクエアのすぐ傍で上演されている。オフ・ブロードウェイというのは、ブロードウェイから離れて上演されるからではなく、客席400人以下の劇場で上演される場合を言うので、今なおオフ・ブロードウェイ・ミュージカルとして、ブロードウェイの劇場街に君臨している。 ニューヨークに行けば、今ではグリニッチではなく、ブロードウェイの50丁目、タイムズ・スクエアのすぐ傍で上演されている。オフ・ブロードウェイというのは、ブロードウェイから離れて上演されるからではなく、客席400人以下の劇場で上演される場合を言うので、今なおオフ・ブロードウェイ・ミュージカルとして、ブロードウェイの劇場街に君臨している。今回は、1971年渋谷に「ファンタスティックス」の為の小屋ジァンジァンができて、主役のエル・ガヨ役で出演し、その後も何度もエル・ガヨとして活躍してきた宝田明が、製作・演出・主演するということで、何とも頼もしいし、心弾む話ではあるが、若い娘が一目でのぼせあがるというハンサム氏の役どころなので、氏の年齢を考えると(失礼ながら)少し心配になった。  物語は、隣同士に住む、父親たち(沢木順、青山明)は息子マット(松岡充)と娘ルイザ(彩乃かなみ)の結婚を望んでいるが、親の意向と知れば反対すると思い、仲の悪い父親同士と思わせる為に、両家の間に壁(本間ひとし)を築く。父親たちの思惑通り、反対されていると思った二人は恋に落ちる。だが、仲たがいしている筈の親の和解をどうするか悩んだ末に、プロの誘拐屋エル・ガヨ(宝田明)を雇って、ルイザを誘拐させて、マットに助け出させてハッピー・エンドにしようと計画する。誘拐劇には老優ヘンリー(光枝明彦)とその弟子(島崎俊郎)もにぎにぎしく登場、計画は大成功! 物語は、隣同士に住む、父親たち(沢木順、青山明)は息子マット(松岡充)と娘ルイザ(彩乃かなみ)の結婚を望んでいるが、親の意向と知れば反対すると思い、仲の悪い父親同士と思わせる為に、両家の間に壁(本間ひとし)を築く。父親たちの思惑通り、反対されていると思った二人は恋に落ちる。だが、仲たがいしている筈の親の和解をどうするか悩んだ末に、プロの誘拐屋エル・ガヨ(宝田明)を雇って、ルイザを誘拐させて、マットに助け出させてハッピー・エンドにしようと計画する。誘拐劇には老優ヘンリー(光枝明彦)とその弟子(島崎俊郎)もにぎにぎしく登場、計画は大成功! 壁も取り払われて自由に行き来できるようになった若者たちは、恋の熱も冷め始め、そこに再び登場したエル・ガヨにルイザはすっかり夢中になってしまう。夢破れたマットは旅に出て、様々な苦労に出会い、やがて身も心も傷だらけになって故郷に帰ってくる。ルイザもエル・ガヨにはまともに相手にされず、実態を見られるようになっている。少しだけ大人になった二人は、初めて互いの現実の姿を認め合い、改めて愛を確認するというハッピー・エンディングとなる。 壁も取り払われて自由に行き来できるようになった若者たちは、恋の熱も冷め始め、そこに再び登場したエル・ガヨにルイザはすっかり夢中になってしまう。夢破れたマットは旅に出て、様々な苦労に出会い、やがて身も心も傷だらけになって故郷に帰ってくる。ルイザもエル・ガヨにはまともに相手にされず、実態を見られるようになっている。少しだけ大人になった二人は、初めて互いの現実の姿を認め合い、改めて愛を確認するというハッピー・エンディングとなる。こう書いてしまうと、ロミオとジュリエットを下敷きにした極めてありふれた恋物語と思われてしまうが、決してそうではない。親子の問題、男女の愛は古今東西変わることはなく、演出如何によっては、古臭い話ではなく、極めて現代的なものとなる。楽曲の素晴らしさもあって、世界中で愛されている小劇場用のこの舞台を、韓国(2004年)、ニューヨーク(2008年)で観た時も、演者と観客と一体となっての高揚感があって楽しかったのを思い出す。  今回の舞台は多少の懸念(偏見)があった私の思いを見事に裏切って、「ファンタスティックス」のもつ良さを知り尽くしての宝田氏の演出と、その熱意に応えた出演者全員の紡ぎだす舞台は、ピアノ(桑原まこ)とハープ(田中淳子)の演奏も歯切れよく、見事に現代版となって甦った。特にロック歌手である松岡充の青年マットは現代に生きる若者の喜びと苦悩をしっかり表現して、舞台を盛り上げていた。司会進行役でもあるエル・ガヨが、時折客席に語りかけるウィットに富む語りかけも、自然体で間合い良く、楽しさ倍増の舞台だった。この後、全国公演が続き、12月には草月ホールでの舞台があるが、近い将来に是非再演を望みたい! 今回の舞台は多少の懸念(偏見)があった私の思いを見事に裏切って、「ファンタスティックス」のもつ良さを知り尽くしての宝田氏の演出と、その熱意に応えた出演者全員の紡ぎだす舞台は、ピアノ(桑原まこ)とハープ(田中淳子)の演奏も歯切れよく、見事に現代版となって甦った。特にロック歌手である松岡充の青年マットは現代に生きる若者の喜びと苦悩をしっかり表現して、舞台を盛り上げていた。司会進行役でもあるエル・ガヨが、時折客席に語りかけるウィットに富む語りかけも、自然体で間合い良く、楽しさ倍増の舞台だった。この後、全国公演が続き、12月には草月ホールでの舞台があるが、近い将来に是非再演を望みたい!<写真提供: 宝田企画> |
|
ネオ・オペラ マダムバタフライX 神奈川芸術劇場 11月14日・・・本田浩子
|
宮本亜門構成・演出のネオ・オペラと聞いて、観に行こうかどうしようか、正直迷った。ミュージカル&オペラと幅広く活躍する氏の、どの舞台を観てもその才能にはいつも感嘆するが、ネオ・オペラと聞くと、どんな趣向があるのか、新し過ぎて奇をてらったものにならないだろうか、プッチーニの歌曲の良さを壊しはしないだろうかと不安な気持ちが先に立ってしまう。 写真にあるように、舞台は板でいくつかに仕切られているだけで、装置らしいものは殆どなく、上手(カミテ)には事務机が並ぶ。見慣れたオペラ「蝶々夫人」とは違うと思ったら、オペラ「マダム・バタフライ」にドキュメンタリーを絡めて、日本における男女格差の問題や、日本女性のあるべき姿を描き出すテレビ番組を作ろうという、何とも思いがけない展開になっていった。プロデューサー内田淳子は、自身の結婚が暗礁に乗り上げていて、子供を職場に連れてきているという設定に生活感が出て、その状況が蝶々夫人の結婚生活の危うさとダブる。他のスタッフたち、局のチーフ・プロデューサー:神農直隆、カメラマン:兼松若人、ディレクター:柳橋朋典、全員の役名が彼らの本名と同じなのも、現実感があって面白い。おまけに、スタッフの一人に「いまどき、マダム・バタフライとは古過ぎる。こんな番組を作ったら、スポンサーが何と言うか!」と言わせるので、ホント、ホント、と思わず頷いてしまう。 写真にあるように、舞台は板でいくつかに仕切られているだけで、装置らしいものは殆どなく、上手(カミテ)には事務机が並ぶ。見慣れたオペラ「蝶々夫人」とは違うと思ったら、オペラ「マダム・バタフライ」にドキュメンタリーを絡めて、日本における男女格差の問題や、日本女性のあるべき姿を描き出すテレビ番組を作ろうという、何とも思いがけない展開になっていった。プロデューサー内田淳子は、自身の結婚が暗礁に乗り上げていて、子供を職場に連れてきているという設定に生活感が出て、その状況が蝶々夫人の結婚生活の危うさとダブる。他のスタッフたち、局のチーフ・プロデューサー:神農直隆、カメラマン:兼松若人、ディレクター:柳橋朋典、全員の役名が彼らの本名と同じなのも、現実感があって面白い。おまけに、スタッフの一人に「いまどき、マダム・バタフライとは古過ぎる。こんな番組を作ったら、スポンサーが何と言うか!」と言わせるので、ホント、ホント、と思わず頷いてしまう。余談だが、数年前に二期会主催のコバケンこと小林研一郎指揮「マダム・バタフライ」を見に行って私は酔いしれたが、共に行った若い友人の感想ときたら、「さすがプッチーニの音楽は素晴らしい!」の一言で、言外に「古い!」という気持ちがあるのがはっきりして、それ以上は話が弾まなかった経験があり、このスタッフの気持ちも良く分かり、まずはそうやって観客にある種の共感を持たせて舞台に引っ張る構成に脱帽した。  さて、舞台は、大手スポンサーの化粧品会社に見せる為のテスト版制作ということで、進んでいく。「ダイジェスト版ですので、全曲は歌わなくて結構です。」という説明が歌い手(全員二期会のオペラ歌手)たちに伝えられるのも何とも愉快だが、それにもめげす、長崎領事シャープレス(大沼徹)と海軍士官ピンカートン(与儀巧)が「広い世界を(ヤンキーは世界のいずこであろうと)」の二重唱を力強く歌う。 さて、舞台は、大手スポンサーの化粧品会社に見せる為のテスト版制作ということで、進んでいく。「ダイジェスト版ですので、全曲は歌わなくて結構です。」という説明が歌い手(全員二期会のオペラ歌手)たちに伝えられるのも何とも愉快だが、それにもめげす、長崎領事シャープレス(大沼徹)と海軍士官ピンカートン(与儀巧)が「広い世界を(ヤンキーは世界のいずこであろうと)」の二重唱を力強く歌う。ゴロー(吉田伸昭)の案内で蝶々さん(嘉目真木子)と下女スズキ(田村)が登場して、結婚式となる・・・蝶々夫人とピンカートンの愛の二重唱「かわいがって下さいね」が響くが、ピンカートンはまだ存在しない未来のアメリカ人の妻にと領事と乾杯をした後だけに、ピンカートンを信じ切って無邪気に歌う蝶々夫人の様子に胸が痛む。  続いての二幕、舞台進行の合間に、プロデューサー内田の離婚寸前のすったもんだの電話が入ったりの混乱が、本国に帰って三年も戻ってこないピンカートンを一途に信じている蝶々夫人の痛々しい姿を浮き彫りにして、自ずと観客が色々と考えざるを得ず、舞台にくぎ付けになってしまう。ゴローは再婚を勧めるし、スズキもピンカートンは戻ってこないと決めているが、蝶々さんはあの方は戻ってみえると信じて疑わず、有名なアリア「ある晴れた日に」を歌う。美しいソプラノが会場に響き渡り、「古過ぎる」と言っていた舞台のスタッフが「ブラボー!」と叫ぶと同時に、会場からも「ブラボー!」の声がかかる。普通のオペラではなく、この番組を試行錯誤しながら制作するスタッフたちを舞台に置くことで、蝶々夫人の悩み苦しみは、そのまま観客の心に染み入り、まさに演者と観客はイヤでも一体になり、身を乗り出して舞台を見守ることになる。 続いての二幕、舞台進行の合間に、プロデューサー内田の離婚寸前のすったもんだの電話が入ったりの混乱が、本国に帰って三年も戻ってこないピンカートンを一途に信じている蝶々夫人の痛々しい姿を浮き彫りにして、自ずと観客が色々と考えざるを得ず、舞台にくぎ付けになってしまう。ゴローは再婚を勧めるし、スズキもピンカートンは戻ってこないと決めているが、蝶々さんはあの方は戻ってみえると信じて疑わず、有名なアリア「ある晴れた日に」を歌う。美しいソプラノが会場に響き渡り、「古過ぎる」と言っていた舞台のスタッフが「ブラボー!」と叫ぶと同時に、会場からも「ブラボー!」の声がかかる。普通のオペラではなく、この番組を試行錯誤しながら制作するスタッフたちを舞台に置くことで、蝶々夫人の悩み苦しみは、そのまま観客の心に染み入り、まさに演者と観客はイヤでも一体になり、身を乗り出して舞台を見守ることになる。そんな感慨に浸っていたら、突然スポンサーが降りたと連絡が入り大騒ぎになる。チーフ・プロデューサーの神農は撮影中止を告げて、スポンサーに会うと言って帰ってしまう。歌手たちも帰ろうとするが、女性プロデューサー内田は、「私がスポンサーを説得するので、撮影を続けたい。協力して欲しい。」と皆に頼み込む。ピンカートンのアメリカ人妻ケイト(鈴木純子)の「私だって舞台衣装をつけて、歌いたいわ。」の一言に誘われるように、再び撮影が始まる。  子供を引き取ろうとピンカートンが妻と領事と共にやってくるが、三年間も待っていてくれた蝶々さんの誠に打たれ、自分の罪の深さにおののいて、会って真実を告げる勇気がない、「さらば、愛の家、花のかくれ家よ」と見事なテノールでアリア「愛の家よ、さようなら」を歌うと、逃げるように立ち去ってしまう。 子供を引き取ろうとピンカートンが妻と領事と共にやってくるが、三年間も待っていてくれた蝶々さんの誠に打たれ、自分の罪の深さにおののいて、会って真実を告げる勇気がない、「さらば、愛の家、花のかくれ家よ」と見事なテノールでアリア「愛の家よ、さようなら」を歌うと、逃げるように立ち去ってしまう。舞台はいよいよ大詰め、蝶々さんは子供を抱きしめ「さよなら坊や(可愛い坊や)」を歌い、子供をスズキに託して自害する。 スポンサーは戻って来るのか、果たして現代に通じる番組になるのか、観客は考えながら劇場を後にする。こういったオペラは初体験だが、古いオペラに風穴を開けるこんな試みは見応えがあって、面白い。海外に持っていったら、どんな反応があるのか、興味が尽きない。 <撮影:林 喜代種> |
|
日本で最後の色気あるロックン・ローラー。桑名正博。・・・・・・・池野 徹
|
 5年前、ニュー・イヤー・ワールド・ロック・フェスティヴァルで、桑名正博は、スポットライトに、ギター1本で、その独特のハスキーヴォイスで、気持ちが乗って「月のあかり」を歌った。身に震えが走った感動に包まれた曲となったのと、桑名正博の歌の実力を確認したのだった。あのやや微笑みの見える色気のある目をしていたのが忘れられない。「セクシー・ヴァイオレットNo.1」の若々しい色気のロックとは違っていたが。 5年前、ニュー・イヤー・ワールド・ロック・フェスティヴァルで、桑名正博は、スポットライトに、ギター1本で、その独特のハスキーヴォイスで、気持ちが乗って「月のあかり」を歌った。身に震えが走った感動に包まれた曲となったのと、桑名正博の歌の実力を確認したのだった。あのやや微笑みの見える色気のある目をしていたのが忘れられない。「セクシー・ヴァイオレットNo.1」の若々しい色気のロックとは違っていたが。1980年代、桑名正博がアン・ルイスと離婚。再婚して世田谷に一時住んでいたことがあり、ジョー山中と共に桑名の家に遊びに行った。若い連中もおり、桑名は自ら蕎麦を作り振る舞っていた。その時、いきなり桑名の鉄拳が若いヤツを襲った。そいつは、桑名の愛用のウヰスキーの携帯ペットケトルを盗んだのだった。血だらけの若いヤツに、「お前欲しければ言え。」と言い「持っていけ」とそいつにケトルを渡したのだった。同じ様な場面を安岡力也やジョー山中と何回か経験している。一瞬の憤りがバイオレンスの爆発になる。しかしその後に対照的な男の優しさを見せてくれる。桑名正博もそんな男だった。 ロックン・ローラーは、痩せてなければならない。その肌に血筋が浮き出て、干涸びてても良い。飢えているだろうか。美味しさを知り、不味さを厭わない。最高を知り、極貧が似合う。持ってるかい。人を驚かす心、人が羨む程の顔と躯、人を惹き込む声、人を動かす歌。カッコいいかい。見かけも中身も、生き方も、死に方も。 酒とドラッグと女とバイオレンスに心酔葛藤し、その血となり肉となり、言い訳の無い生き様を闘った男。ロックンローラー、ニルヴァーナのカート・コベイン以来だ。歌とギターのうまい男、桑名正博が消えた。悔しい。内田裕也のロックの三銃士を失った心情は、いかばかりであろうか。 <写真は39th NYWRFでの桑名正博のラストステージ Jan.1.2012 撮影:池野 徹> |