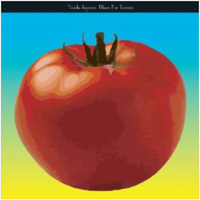|
多彩なパンチを繰り出した、ミック・ジャガーの「スーパーヘヴィ SuperHeavy」
・・・池野 徹 |
||
 デビュー以来50年目を迎えた「ザ・ローリング・ストーンズ」の 今や世界のロック界のスーパースターであるミック・ジャガーが久方ぶ りに動いた。ストーンズの歴史的に見るなら、1963年デビューし て、60年代後半から、70年代初めのストーンズの置かれた ミュージック・シーンのデカダンス性とか、ロックへのファナティックな 感じが、やたらとカッコ良かったのだ。その頃のストーンズは名声は手 に入れたが、世間に媚びてない生き様が良かった。その後はビッグ・ヒットと共に、まさにリッチになったストーンズは、音楽性のレベルはキー プしていたが、何かサムシングの部分が影を潜め、ライヴ・パフォーマ ンスに傾倒して、ニュー・エキサイティング性、ニュー・アグレッシブな面 が薄れていたと思う。 デビュー以来50年目を迎えた「ザ・ローリング・ストーンズ」の 今や世界のロック界のスーパースターであるミック・ジャガーが久方ぶ りに動いた。ストーンズの歴史的に見るなら、1963年デビューし て、60年代後半から、70年代初めのストーンズの置かれた ミュージック・シーンのデカダンス性とか、ロックへのファナティックな 感じが、やたらとカッコ良かったのだ。その頃のストーンズは名声は手 に入れたが、世間に媚びてない生き様が良かった。その後はビッグ・ヒットと共に、まさにリッチになったストーンズは、音楽性のレベルはキー プしていたが、何かサムシングの部分が影を潜め、ライヴ・パフォーマ ンスに傾倒して、ニュー・エキサイティング性、ニュー・アグレッシブな面 が薄れていたと思う。ミックは1985年には、ソロアルバム「She's The Boss」を 出したり、独自に動いたりした時期はあるが、本格的にバンドを組んでレコーディングしたのは今回の「SuperHeavy」が初めてである。ブルースベースのストーンズは、勿論今まで他のジャンルのサウンドは積極的に取り入れて来たが、はっきりと、ストーンズから離れて、他ジャンルに挑戦したミックにとっては、今回のこのアルバムは、まさに注目すべき点なのである。一方で相棒のキース・リチャーズが、 皮肉の笑いを浮かべているのが視えては来るのだが。 ミック・ジャガーは、元ユーリズミックスのディヴ・スチュワートと共同プロデュース。その道のジャンルの本格派のメンバーを選出した。 ジャニス・ジョップリンの再来と云われたUKのソウル・シンガー、 ジョス・ストーンが加わり、また、ボブ・マーリーの7男、ダミアン・マーリーと「スラム・ドッグ・ミリオネア」でオスカー受賞した、インド映画音楽界の若き巨匠、A.R.ラフマーンいう異色キャスティングのユニークなバンドになった。ジャマイカのデイヴ・スチュワートの家で「音の理想郷」についてミックと語り合って「世界一複雑なレコーディングだった」と云わしめた熱の入ったセッションだった様 だ。全17曲のアルバムの日本盤は、ボーナス・トラック入りである。 一言で云えば、ストーンズ・ロックがエスニック・ロックに変身したと言える。ミックのヴォーカルは、まるで多彩なパンチを繰り出すごとく、ストーンズを吹っ切って楽しげに骨太にロックしている。そのサウンドは、ダミアンのレゲエをベースに、ラフマーンのインド風の味付けで、ミックとジョスのヴォーカルが噛み合って、ディヴのギターがサポートして、新しいロック・クオーリティを創りだしている。  シングル・カットされた「Miracle Worker」の映像を見たが、完全なレゲエ・ロックだ。ミックは、ショッキング・ピンクのスーツを着て、パワフルに奔放にムーヴィングしてる。懐かしのデカダンスの世界が視えたのである。また、ジョス・ストーンとの掛け合いは、かつてのティナ・ターナーを彷彿させ、ダミアン・マーリーのレゲエトーンに乗って久しぶりにミックらしいステージを繰り広げてる。 シングル・カットされた「Miracle Worker」の映像を見たが、完全なレゲエ・ロックだ。ミックは、ショッキング・ピンクのスーツを着て、パワフルに奔放にムーヴィングしてる。懐かしのデカダンスの世界が視えたのである。また、ジョス・ストーンとの掛け合いは、かつてのティナ・ターナーを彷彿させ、ダミアン・マーリーのレゲエトーンに乗って久しぶりにミックらしいステージを繰り広げてる。トラックリストは、タイトル曲「SuperHeavy」からはじまり、3曲目に「Miracle Worker」が入り、「Satyameva Jayathe」はアフリカン・レゲエ風で、「Beautiful People」でボブ・マーリー風レゲエをダミアンが表現。「I Can't Take It No More」でミックがストーンズ節を出し、「Mahiya」では、ラフーマンとダミアンで、東洋イスラム風の匂いの強い曲で、「Hey Captain」では、ミック、ジョス、ダミアン、ラフマーンでパワフルな掛け合いソングだ。日本盤ボーナスとなってる「Never Gonna Change」では、デイヴ・スチュワートのアコースティック・ギターに、ミックの「Wild Horses」的な、ストーンズらしい曲でこのアルバムは締めくくられている。 バンド名の「スーパーヘヴィ」は、ダミアン・マー リーの口癖だった。意味的には、ボクシングのヘヴィー級を超す程の、 最強のとか、超カッコイイと云う事だろう。ジャマイカン・レゲエ、オリエンタル・インド、ソウルフル・シャウト、そのリズムのコンバインの中で、しっかりバックボーンは、インストゥルメンタルを含めて、ロックが息づいている。ミックは、ティナ・ターナー、デヴィッド・ボウイ、 マイケル・ジャクソン等とデュエットした時など、他のシンガーと歌う 時は、異常に意識して、負けじと歌うので、今回のトリプル、いやフォースでの掛け合いには、パワーの入り具合や、その声のシャウトし具合も、聴くのも楽しいものである。まさにSuperHeavyある。
|
|
フレンチ・ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」を楽しむ・・・本田 浩子
|
 ご存知シェークスピィアの「ロミオとジュリエット」が、作詞・作曲そして演出も手がけるジェラール・プレスギュルヴィック作のフレンチ・スペクタクル・ミュージカルとして、2001年パリで初演されるや、大変な話題を呼び、オーストリア、オランダ、ハンガリー、ロシア、韓国など世界20数か国で上演されている、日本では宝塚歌劇団星組が2010年に初演、今年は雪組による上演され、大好評だったのは記憶に新しいが、今回は宝塚と同じく小池修一郎演出による、男女混合バージョン(?)での公演が実現、赤坂ACTシアターで上演された。 ご存知シェークスピィアの「ロミオとジュリエット」が、作詞・作曲そして演出も手がけるジェラール・プレスギュルヴィック作のフレンチ・スペクタクル・ミュージカルとして、2001年パリで初演されるや、大変な話題を呼び、オーストリア、オランダ、ハンガリー、ロシア、韓国など世界20数か国で上演されている、日本では宝塚歌劇団星組が2010年に初演、今年は雪組による上演され、大好評だったのは記憶に新しいが、今回は宝塚と同じく小池修一郎演出による、男女混合バージョン(?)での公演が実現、赤坂ACTシアターで上演された。パリ初演版をDVDで観た時は、全編歌で綴られていくのだが、その楽曲の素晴らしさ、そして舞台を縦横無尽に駆け巡り、パワフルに歌う演者たちに圧倒された。甘美な悲劇ではあるが、若者達の群像劇ともいえる斬新な演出に、言葉のハンディを超えて楽しんだ記憶がある。 そんな訳で、9月28日のACTシアターに足を運びながら、期待とは裏腹にあのフランス勢のパワーを超えられるか、少し心配になる。配役を見るとロミオの親友のベンヴォーリオは若手とはいえ、実力、経験充分な浦井健治が一人で務めるが、ロミオは城田優と山崎育三郎、ジュリエットは昆夏美とフランク莉奈、ティボルトが上原理生と平方元基、マーキュシオが良知真次と石井一彰と主だった役どころの若者たちは全てダブル・キャストになっているのが不思議だったが、舞台が始まると、とにかく激しいダンスとパワフルなロックを歌いながら、舞台を駆け巡るのにはいくら若さがあっても、やはりダブル・キャストは正解と言えるだろうと納得。(写真全景参照) 若者たちが歌う激しいロックとは打って変わって、石川禅のキュビュレット卿、涼風真世のキュビュレット夫人、ひのあらたのモンタギュー卿、大鳥れいのモンタギュー夫人、中山昇のヴェローナ大公たちは美しいバラードを心行くまで楽しませてくれる。殆ど出ずっぱりの死のダンサー(中島周・大貫勇輔のダブル・キャスト)の見事な動きが、ストーリーにしっかりと陰影をつけ、見る者に悲劇を強く訴える一方、ジュリエットの乳母役の未来優希はコミカルな演技と圧倒的な歌唱力で客席を沸かせる。ロレンス神父役の安崎求は恋に燃える若い二人の良き理解者でありキュビュレット家とモンタギュー家の和平を願う者だったが、思いもかけずロミオとジュリエットの死を前にして、神よ私はこれから何を信じていけば良いのでしょうと悲嘆にくれて歌う姿は(写真参照)、災害が続いて思い悩む現在の私たちの気持ちにもリンクして、心を揺さぶる。 若者二人の死を悼む両親たちは、両家間の憎悪が悲劇の原因と思い知り、互いに手を差し伸べ、和解する幕切れは悲しい中にも、希望が垣間見られ爽やかなエンディングとなり、カーテンコールのコーラス「エメ(Aimer)」では、スタンディング・オヴェイションで会場が沸き返った。 写真:宮川 舞子 |
|
ブライアン・ジョーンズ・トリビュート・バンド
「Jajouka (ジャジューカ)」 ワンマン・ライヴが大阪で再び!!」・・・犬伏 功 |
|
MPCトークス 2011年4月号でも取り上げたブライアン・ジョーンズ・トリビュート・バンド「Jajouka(ジャジューカ)」が帰ってきた!
 2月に行われた≪ロックン・ロール・サーカス≫完全再現ライヴに引き続き、大阪本町にあるライヴ・ハウス「Beggar's Banquet」で10月1日に行われたライヴをレポートしたい。 「Jajouka(ジャジューカ)」とは彼らはジョーンズ没後40年となる09年にシタール・プレイヤーで熱心なブライアン・フリークの片山健雄を中心に結成されたジョーンズのトリビュート・バンド。メンバーは以下の4人だ。 ・イクオ・ジャガー(ヴォーカル). ・ブライアソ健雄ジョーソズ (ギター、シタール、ダルシマー、リコーダー、ハープ、マラカス他) ・センセイ・リチャード (ギター) ・ビル・タケボン (ベース) ・チャーリー・IKKI (ドラムス) 前回も書いた通り、彼らのセット・リストに「ブラウン・シュガー」も「スタート・ミー・アップ」もない。あくまでもブライアンがいたストーンズを追求するのみ。今や本家のライヴでも絶対聴けない、いや当時ライヴで演奏すらされなかったナンバーまでが聴けるのだからたまらないのだ。 今回のショーは≪Blues & R&B≫≪Rock'n'Roll Circus & more≫の2部構成だった。ではセット・リストをご覧いただこう。(*は、ブライアソのギター以外の使用楽器及び、ギターの変則チューニング)。 【1st Stage】Blues & R&B 1.Heart Of Stone 2. Mercy Mercy 3.Everybody Needs Somebody To Love〜Pain In My Heart 4.I Can't Be Satisfied *Open G(Slide) 5.Little Red Rooster *Open G(Slide) 6.What A Shame *(Slide) 7.It's All Over Now 8.I Want To Be Loved *(Harp) 9.One More Try *(Harp) 10.I Wanna Be Your Man(彼氏になりたい)*Open E(Slide)& Chorus 11.I'm Moving On *Open E(Slide) いきなり「ハート・オヴ・ストーン」である。ストーンズが最初に個性を確立したオリジナル曲だが、エンディングでブライアソがボトルネックを取り出した。これはリリース版以前に収録された、いわゆる「メタモーフォーシズ」ヴァージョンをチラ見せしたのか・・・。いきなりマニアックな展開だ。そして続くのは66年ツアーの重要ナンバーだった②が。なんかもう堪らない展開だ。そして〈3〉ではフル・ヴァージョンを聴かせると見せかけておいて、「ペイン・イン・マイ・ハート」へのメドレーへとなだれ込む。これは初期ストーンズのお約束ともいうべき流れだ。そしてブライアソのボトルネックをフィーチャーした3曲、マディ・ウォーターズ版イントロで意表を突く〈4〉から〈5〉、そして〈6〉と続く。初期ストーンズの卓越したアレンジ力が光る、ヴァレンチノスを超えるキャッチーさが魅力の≪〈7〉では一丸となったバンドの結束力を、そしてデヴュー・シングルのB面曲〈8〉、全米席巻の象徴となった65年のアルバム『アウト・オヴ・アワ・ヘッズ』のラストを飾る⑨で絶妙のハープを披露する。しかし〈6〉〈9〉ともに、なんとマニアックな選曲なこと! そして前半を締めくくるのがレノン/マッカートニーのナンバーをディープに仕上げた〈10〉、初期ライヴの大定番〈11〉。〈10〉のエンディングはご想像の通りアーサー・ヘインズ・ショー出演時の演奏に準じたものだ。 【2nd Stage】Rock'n'Roll Circus & more 1.Sitar Solo〜Paint It, Black(黒くぬれ!)*(Sitar) 2.Mother's Little Helper *(Sitar) 3.Lady Jane *(Dulcimer) 4.No Expectations *Open E(Slide) 5.Salt Of The Earth(地の塩)*Open E(Slide)& Vocal 6.19th Nervous Breakdown(19回目の神経衰弱) 7.Parachute Woman 8.Ruby Tuesday *(Recorder) 9.Sympathy For The Devil(悪魔を憐れむ歌)*(Maracas & EG) 《encore 1》 10.Jumpin' Jack Flash 《encore 2》 11.(I Can't Get No)Satisfaction  暫しの休憩を挟み、ブライアソによるシタールの独奏で幕が再び開くと「黒くぬれ!」のイントロへと繋がっていく。分かっちゃいるけど気持ちいい瞬間だ。そして<2>へと流れるが、シタールをフィーチャーした②を生で聴けるとは格別だ。<2>と同じ『アフターマス』からの〈3〉では遂にダルシマーが登場! エド・サリヴァン・ショーでの姿を思い起こさせるブライアソの姿。折角ならピンストライヴのスーツで片手には包帯を、とは悪ノリが過ぎるだろうか・・・。 そして前回の≪サーカス編≫で聴けた〈4〉〈5〉が再び登場。ここでの彼らは≪サーカス≫を忠実に再現するというより、あの時点でブライアンがリーダーだったらという仮説も含め演奏しているのではないか。そういう想像を巡らせるのも実に楽しいと思う。 そして、ここでいきなり〈6〉へと時代が戻る。チャーリー・IKKIの細やかなシャッフルとビル・タケボンのグリッサンドにニンマリしながら、再び≪サーカス≫の〈7〉へ。ここでのブライアソのスライド・ギターは絶品だ。そして後半の最後を彩るのはお待ちかねのリコーダーが堪能できる〈8〉。「みんながリコーダーばかり見てる」とはイクオの弁だが、観客全員が小学生時代にリコーダーを体験しているはずで、巧みな表現の凄さを実感しているのだ。そしてイクオの個性が溢れた日本語で歌われる<9>で会場のテンションはピークに。ここではブライアソとセンセイ・リチャードによる、オリジナルとは違う“弾き分け”にも要注目だ。そして2回のアンコール、まだ端正で安定感のあった頃を蘇らせた〈10〉、そして説明不要の〈11〉へと続く・・・。 このジャジューカというバンドの魅力は、ブライアソによるブライアン・ジョーンズの飽くなき追求はもちろんだが、決してマニアックで閉鎖的なものへと陥らないのはイクオの持つエンターテイメント性との抜群のバランスなのではないかと思う。この日、中盤で観客から「ジャジューカってどういう意味?」という質問が飛んだが、これはこのショーが幅広いオーディエンスを擁していることを証明している。ストーンズに詳しくなくても思い切り楽しめ、ヘヴィーなリスナーほどニヤリと笑みを浮かべてしまうゴキゲンなバンド、それがジャジューカなのである。 |
|
大感動!≪沢田研二 LIVE2011〜2012≫
東京国際フォーラム・ホールA 10月2日・・・町井ハジメ |
 10月2日夕方、有楽町の駅を降り立つと多くの女性が同じ方向へと足を進めていた。行き先は東京国際フォーラム。沢田研二のLIVE会場だ。今回はいつものジュリーのLIVEとは一味違う。ゲストとして森本太郎(タロー)、岸部一徳(サリー)、瞳みのる(ピー)が全曲参加するのだ。40年以上前、グループ・サウンズの王者としてブームの頂点に君臨した、あのザ・タイガースで一緒だったメンバーとともに、全曲タイガース時代のレパートリーを演奏するという。これを聞いて血が騒がないはずが無い。会場へ向かう足取りも自然と早足になる。 10月2日夕方、有楽町の駅を降り立つと多くの女性が同じ方向へと足を進めていた。行き先は東京国際フォーラム。沢田研二のLIVE会場だ。今回はいつものジュリーのLIVEとは一味違う。ゲストとして森本太郎(タロー)、岸部一徳(サリー)、瞳みのる(ピー)が全曲参加するのだ。40年以上前、グループ・サウンズの王者としてブームの頂点に君臨した、あのザ・タイガースで一緒だったメンバーとともに、全曲タイガース時代のレパートリーを演奏するという。これを聞いて血が騒がないはずが無い。会場へ向かう足取りも自然と早足になる。会場であるホールAに入ると、5000席はあるという場内は既に満員。16時30分の開演時刻になり、場内には聴き覚えのあるジュリーの歌声が流れた・・・「G.S.I LOVE YOU」だ。同名タイトルのアルバムが発売されたのは、80年の暮。ここ有楽町のシンボルでもあった日劇の取り壊しが決定し行なわれた「さよなら日劇ウエスタン・カーニバル」で瞳みのるを除くザ・タイガースのメンバーが一堂に会したのが翌81年1月の事だった。この曲を聴いて、その頃の事を思い出されたファンの方も多かっただろう。そんな思いにふけっている内に、全員色違いのジャケットに身を包んだメンバーがステージに登場。♪ミスタァ〜〜〜ムーンラーイト♪、シャウトを決めるジュリーの周りには、タローが、サリーが、そしてピーがいる。ジュリー、いやザ・タイガースのファンが長年夢にまで見たLIVEが今まさに幕を開けた。この曲はビートルズのカヴァーだが、京都の頃のタイガース、すなわちファニーズ時代のレパートリーでもある。続くデイヴ・クラーク・ファイヴのカヴァー「Do You Love Me」ではピーのドラミングが全開。ブランクをまったく感じさせない叩きっぷりは見事だ。サリーも得意の低音ヴォイスを聞かせる。タイガース時代と同じカール・ヘフナーのベースの音もよく出ている。黒いストラトキャスターを持ったタローも楽しそうだ。ジュリーのアクションもノッている。タイガース時代の18番、ローリング・ストーンズの「Time Is On My Side」ではジュリーのジャンプに場内が沸く。MCではジュリーのギャグも飛び出し絶好調。サリーも今日は俳優・岸部一徳ではなくベーシスト・サリーだ。タローは数年間にわたって毎月LIVEを重ねて来ており演奏に不安は無い。そして40年ぶりにファンの前に姿を見せたピー(得意の中国語で挨拶した)には一際大きな声援が飛ぶ。 次の「僕のマリー」からはタイガースのオリジナル曲が登場。この曲はタイガースの記念すべきデビュー曲。当時を思わせるジュリーの甘い歌声は場内のファンを酔わせた。コーラスにも厚みと貫禄がある。タローがハーモニカを演奏する「モナリザの微笑」、主演映画の主題歌だった「銀河のロマンス」と大ヒット曲が続く。「坊や祈っておくれ」は、サリー作詞、タロー作曲による反戦のメッセージを込めた曲で、当時ステージでは演奏されていたものの、レコードではライヴ盤以外では公式には発表されていなかった(後にデモテイクがCD化された)。ジュリー・サリー・タローの素晴らしいコーラスワークを存分に聴かせた。 続いては洋楽カヴァー。タローの歌でDC5の「Because」をしっとりと聴かせた後は、ジュリーによるワイルドなストーンズ・ナンバー「Satisfaction」を。ラチャス・ブラザースの歌で有名な「Justine」では、ピーがドラムセットから降りてセンターでヴォーカルを披露。奇しくも71年1月24日、日本武道館でのビューティフル・コンサートでもピーが歌った曲だ(その時はハーマンズ・ハーミッツのカヴァー『ヘンリー八世君』とのメドレー形式)。ピー!ピー!という観客とのコール&レスポンスも40年前と同じ。あの時ピーはステージ上で「僕にとってこれが最後の舞台です・・・最後の声、出してください!」と言い、その言葉通り、≪瞳みのる=ピー≫は封印された。しかしピーは、今、こうして私たちの前に最高の形で帰って来てくれた。ジュリー、タロー、サリーは一緒にプレイする事で、そして満員の観客は拍手と歓声でピーを温かく迎え入れていた。演奏が終わるといったんメンバーが下がり、盛り上がったまま前半が終了。 約15分の休憩の後、ローリング・ストーンズの「Little Red Rooster」のBGMにのって、胸元と袖口に刺繍をあしらったタキシードに着替えたメンバーがステージ上に現れた。「淋しい雨」からスタートした後半は、「風は知らない」「散りゆく青春」と、タイガース後期のシングルB面に収められていた言わば隠れた名曲が続いた。次に演奏された「花の首飾り」では、ジュリーがヴォーカルを担当。聴き慣れていた歌も新鮮な気持ちで聴く事が出来た。スローな曲が終わると間髪入れずにハードなリフが炸裂。アルバム『ヒューマン・ルネッサンス』に収録されていたロック・ナンバー「割れた地球」だ。さらにハードな「怒りの鐘を鳴らせ」「美しき愛の掟」では、ロック・バンドとしての実力をまざまざと見せ付けた。MCのあとはタロー作詞作曲による「青い鳥」、ステップも飛び出す初期のヒット曲「シーサイド・バウンド」、そしてタイガースの人気を決定付けたとも言える大ヒット曲「君だけに愛を」が登場。もはや伝説となっている♪君だけーにー!♪というジュリーの指差しパフォーマンスに観客の目線は釘付けとなり、場内はこの日一番の盛り上がりを見せた。続いてタイガースのラスト・シングルでもあった「誓いの明日」が演奏されると、この夢のような時間も終わりに近づいて来ている事を実感した。この曲を聴きながらビューティフル・コンサートで泣きながらこの曲を聴いた当時のファンの気持ちがオーバーラップし、心の中にこみ上げてくるものがあった。演奏終了後メンバーは退場。場内にはアンコールの拍手が鳴り響いていた。 鳴り止まぬ拍手と声援に応えてメンバーが登場。改めてメンバー紹介が行なわれ、 一人一人にさらに大きな拍手が送られた。サリーのベースで始まったのは、軽快なロックンロール「シー・シー・シー」。観客も手拍子で雰囲気を盛り上げる。続いての「落葉の物語」は「君だけに愛を」のB面ながら人気の高い曲。格調高いイメージがタイガースにぴったりの曲だ。そしてピーのドラムが、「ラヴ・ラヴ・ラヴ」のイントロを叩き始めた。ファンなら誰でも知っているタイガースのLIVEでのクロージング・ナンバーだ。♪時はあまりにも早く過ぎ行く♪という歌詞にある通り、素晴らしかったこの夜のLIVEも、この曲で本当にラスト。約2時間で全24曲、タローもサリーもピーも最後まで力強い演奏を聴かせてくれた。ジュリーも実に気持ち良さそうに歌っていたように感じた。ファンが右手を掲げて作ったLの字が場内を埋め尽くし、最高のロック・ショーの幕が下りた。今後も日本各地でLIVEを重ね、来年1月24日には、40年前に解散の場所となった日本武道館LIVEが控えている。 写真:noko |
|
JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャルVOL.24
『感動を呼ぶヴァイオリン』〜MASAKI・スペシャルLIVE〜・・・町井 ハジメ |
 10月13日、オーストラリアと日本で活躍しているというヴァイオリン・アーティスト“MASAKI”によるスペシャルLIVEを鑑賞するため、東京・丸の内にあるJVCケンウッド・ショールームに出向いた。開場時間の18:45を前に、すでに会場には人だかりが出来ており、彼の人気の高さを物語っていた。 10月13日、オーストラリアと日本で活躍しているというヴァイオリン・アーティスト“MASAKI”によるスペシャルLIVEを鑑賞するため、東京・丸の内にあるJVCケンウッド・ショールームに出向いた。開場時間の18:45を前に、すでに会場には人だかりが出来ており、彼の人気の高さを物語っていた。横浜生まれシドニー育ち、6歳でヴァイオリンを始めたというMASAKIは、オーストラリア・ユース・オーケストラ等のメンバーとして世界ツアーに参加し、オペラハウス、カーネギーホール、ロイヤル・アルバートホール、コンセルトヘボウ等、世界各国の伝統あるコンサートホールでの演奏を経験。中学在学時にオーストラリアで認定されているプロ認定資格を得たという実力派プレーヤー。プレーヤーとしてだけで無く、作曲もこなし自作自演のアルバムもリリースしており、今年に入り、2月23日に通算4枚目のアルバム『7000万年の岩』を発表。3月21日には日本でのコンサートを予定していたが、震災により断念。改めて10月23日にコンサートを行なうべく来日を果たした。この日のスペシャルLIVEは、MASAKI曰く、コンサートの“お試し”としても楽しめるように、と彼自身が構成してくれたそうだ。 この日は、ニューアルバム収録曲を中心に8曲もの演奏を披露。彼の奏でるヴァイオリンから生み出されるメロディーには、何故か懐かさを覚えた。彼が幼い日を過ごした日本に対する郷愁が、曲に込められていたからかも知れない。 どの曲も人間味ある優しいメロディーで、作曲家としての彼のセンスの良さを感じた。「ぼくと犬とねずみのポルカ」や「スイカの音」など、彼が日常で感じた事を題材にした曲も多い。鈴木道子氏とのトークでも純粋で飾らない彼の人柄を窺い知る事が出来た。演奏面でも、まるで彼の体とヴァイオリンとが一体化しているかと思えるほど素晴らしく、オーディエンスが皆、心地よさそうに耳を傾けていた姿が印象深い。タイトルにもある通り、まさしく“感動を呼ぶヴァイオリン”であった。 演奏終了後も続くオーディエンスの盛り上がりに応え、MASAKIは予定には無かったアンコール曲「じゃからんだ」まで披露。大喝采でこの日のLIVEが幕を閉じた。私自身も、この機会にMASAKIが創り出す音楽と初めて出会う事が出来て良かったと感じたし、この10月にニューアルされたばかりのJVCケンウッド・ショールームにとっても、オープニングに相応しいライヴになったと思う。  =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) MASAKIのヴァイオリンの音色はいつ聴いても優しさに満ち溢れている。それは彼自身の優しさでもあり、曲を作る時にも心からの愛を込めて題材と向き合っているせいだろう。だから彼が奏でると、そこに表現されたすべてのものが愛らしく思えてくる。リニューアルされた会場も以前よりすっきりした感じで、心なごむひと時だった。(滝上 よう子) |


 The Grandfathersのメンバーとして1985年より活動、解散後の92年からはソロのシンガー・ソングライター&ギタリストとして2006年までに10枚のアルバムをリリース、多くのファンを魅了し続けてきた青山陽一。
The Grandfathersのメンバーとして1985年より活動、解散後の92年からはソロのシンガー・ソングライター&ギタリストとして2006年までに10枚のアルバムをリリース、多くのファンを魅了し続けてきた青山陽一。 (青山)「そうです。特に陽水さんが大好きでしたね。なんか、信じてもらえないかもしれませんが(笑)、当時は<激しいロック>が苦手だったんですよね。でも、すぐに、その意識を変えてくれたのが、ご多分に漏れずビートルズとの出会いでした。『アビー・ロード』とか衝撃的でしたよ。ビートルズは特に『ホワイト・アルバム』以降の後期が好きで、曲単位で言うと「ディグ・ア・ポニー」とか「ドント・レット・ミー・ダウン」とか、あのあたりですね」
(青山)「そうです。特に陽水さんが大好きでしたね。なんか、信じてもらえないかもしれませんが(笑)、当時は<激しいロック>が苦手だったんですよね。でも、すぐに、その意識を変えてくれたのが、ご多分に漏れずビートルズとの出会いでした。『アビー・ロード』とか衝撃的でしたよ。ビートルズは特に『ホワイト・アルバム』以降の後期が好きで、曲単位で言うと「ディグ・ア・ポニー」とか「ドント・レット・ミー・ダウン」とか、あのあたりですね」 (青山)「5枚ですかぁ、うーん(笑)。まずはエリック・クラプトンから1枚ですかね。デレク&ザ・ドミノスの『レイラ』、これは外せないでしょう。もともと僕ってセッションっぽい音楽が好きでして、このアルバムなんかモロにドンピシャでしょ。まあ、その一方でXTCみたいな「箱庭」的なサウンドも好きなんですけど。そういった意味ではトッド・ラングレンも僕にかなり影響を与えたミュージシャンですね」
(青山)「5枚ですかぁ、うーん(笑)。まずはエリック・クラプトンから1枚ですかね。デレク&ザ・ドミノスの『レイラ』、これは外せないでしょう。もともと僕ってセッションっぽい音楽が好きでして、このアルバムなんかモロにドンピシャでしょ。まあ、その一方でXTCみたいな「箱庭」的なサウンドも好きなんですけど。そういった意味ではトッド・ラングレンも僕にかなり影響を与えたミュージシャンですね」 (青山)「スティーヴ・ウィンウッドですね。ということでトラフィックの『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』。これは本当にいつ聴いても最高ですよ。ウィンウッドっていうと、ヴォーカルとハモンド・プレイにばかり注目が集まるわけなんですが、ギタリストとしても僕は高く評価してます。彼のギター・プレイって、決して技巧派というか、格別上手いってわけでもない。でも、ツボを知ってるんですよね。たどたどしくって、突っかかる感じ、っていうのかな。そこが黒っぽくて逆に最高なんです。あのテイストは、どんなにテクニックを身に付けた人も出すことはできないという。もう唯一無二、孤高の存在ってやつですかね。白人にしか出せない黒人のサウンドとでも言おうか、とにかく一般のギタリストのロジックでは考えられない」
(青山)「スティーヴ・ウィンウッドですね。ということでトラフィックの『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』。これは本当にいつ聴いても最高ですよ。ウィンウッドっていうと、ヴォーカルとハモンド・プレイにばかり注目が集まるわけなんですが、ギタリストとしても僕は高く評価してます。彼のギター・プレイって、決して技巧派というか、格別上手いってわけでもない。でも、ツボを知ってるんですよね。たどたどしくって、突っかかる感じ、っていうのかな。そこが黒っぽくて逆に最高なんです。あのテイストは、どんなにテクニックを身に付けた人も出すことはできないという。もう唯一無二、孤高の存在ってやつですかね。白人にしか出せない黒人のサウンドとでも言おうか、とにかく一般のギタリストのロジックでは考えられない」 (青山)「高校の頃、愛聴したなかから、そうですねぇ、リトル・フィートの『ザ・ラスト・レコード・アルバム』、これにしましょう。これもクラプトン経由でたどり着いたアルバムなんですよ」
(青山)「高校の頃、愛聴したなかから、そうですねぇ、リトル・フィートの『ザ・ラスト・レコード・アルバム』、これにしましょう。これもクラプトン経由でたどり着いたアルバムなんですよ」