|
「映画吹替物語」(1) 本田 悦久 (川上 博)
|
 ここで云う「吹替」は、外国映画の日本語吹替のことではない。セリフは俳優の声を残して、主に歌の部分にプロの歌手などの歌声を使うことを意味する。その場合、吹替えた歌手の名前をクレディット(公表)する場合と、しない場合がある。しない場合は、歌を提供した歌手は「ゴースト・シンガー」ということになる。 ここで云う「吹替」は、外国映画の日本語吹替のことではない。セリフは俳優の声を残して、主に歌の部分にプロの歌手などの歌声を使うことを意味する。その場合、吹替えた歌手の名前をクレディット(公表)する場合と、しない場合がある。しない場合は、歌を提供した歌手は「ゴースト・シンガー」ということになる。映画「雨に唄えば」(1953) を思い出して頂こう。サイレント(無声映画) 時代には大スターとして鳴らした女優が、トーキーの幕開けに際して、声が悪くて使いものにならず、彼女の声がすべて吹替えられた裏話が描かれていた。スクリーンの中の人間が喋りだした1927年頃から、スターの声や歌の吹替物語が始まったわけだ。 歌手ではないが、一応歌もこなし、画面で歌うスターはけっこう多い。俳優ともなれば歌も演技のうち、ということになるのかもしれない。しかし、歌いたがらないスターも、又踊れても歌は苦手というスターもいるだろう。歌えても役柄に相応しくないというケースもあるだろう。そんな時、吹替の出番となる。そこはステージのライヴ・パフォーマンスと違って、映画ならではの芸当が容易である。天はスターに美貌と美声の二物を与えることが出来るのだ。 ☆ゴースト・シンガーの女王マーニ・ニクソン 吹替の実例を探ってみると、女優の場合が意外と多いのに気づく。 「王様と私」(1956)、「ウエスト・サイド物語」(1961)、「マイ・フェア・レディ」(1964) の3大名作のヒロインの歌を吹替えたマーニ・ニクソン。 彼女の歌声吹替の初仕事は「秘密の花園」(1949) のマーガレット・オブライエンだった。それからマリリン・モンローの「紳士は金髪がお好き」(1953) で、マリリンが歌う「ダイヤは最良の友」の高音部の一部。聴いてみると、マリリンの声とは違うのが判る。 本格的な吹替は「王様と私」のアンナ役デボラ・カー。マーニとデボラは合意の上で協力しながら進めたので、出来上がりもよかった。翌1957年にデボラ・カーが歌手の役で主演した「めぐり逢い」でも、マーニのお世話になった。 「ウエスト・サイド物語」のマリア役ナタリー・ウッドの場合は、ナタリーが歌に自信を持っており、本人による録音が殆ど終わっていた。その後に吹替の話が浮上し、ナタリーに知らせずに行われたため、彼女は激怒したという。 ナタリーだけでなく、アニタ役リタ・モレノの一部にも関わった。因みにトニー役リチャード・ベイマーの歌はジミー・ブライアントという歌手だった。スクリーンには出なかったナタリー自身の録音済みの歌声は、DVD時代になって発売された2枚組DVDのMaking…に収録されていた。 主役の二人が自分で歌わなくてもミュージカルが出来るのだから、映画というのは器用なものだ。ナタリー・ウッドは「ジプシー」(1962)、「美人泥棒」(1967) では自声で歌っている。「ジプシー」ではママ役のロザリンド・ラッセルが、ブロードウェイの「ワンダフル・タウン」等に出ていたミュージカル・スターであるにも拘わらず、同業の女優リサ・カークによって吹替えられ、しかも1曲だけ自分の歌が残されるという複雑さだった。 舞台では、ジュリー・アンドリュースで大当たりした「マイ・フェア・レディ」のイライザ役は、映画化に際してオードリー・ヘップバーンが起用された。ブロードウェイのステージで、オードリーがイライザ役で歌うということは考えにくいが、スクリーンでは、彼女のパーソナリティに合ったゴースト・シンガーの声を得て、のびのびと歌い、ミュージカル映画のヒロインを巧みにこなした。そのサウンドトラック盤にもクレディットされてはいないが、オードリーの陰唄の主がマーニ・ニクソンであることは、早くからファンに知られていた。しかし、オードリーの歌声を使う案もあったようで、劇中の2曲をやや低めの声で歌ったオードリー自身の録音が残されており、その後に発売された「マイ・フェア・レディ」のレーザー・ディスクやDVDに特典として収録されている。「マイ・フェア・レディ」以前のオードリーは、「麗しのサブリナ」(1954) で、「バラ色の人生」をフランス語で口ずさんでおり、フレッド・アステアと共演した「パリの恋人」(1957) でも、彼女の歌声はたっぷり使われて、サントラ盤にもその名が記載されている。 マーニ・ニクソンは、まさにゴースト・シンガーの大スターといったところだが、「マイ・フェア・レディ」のオードリーがアカデミー賞にノミネートもされなかったのは吹替のせいだとの報道が流れて、オードリーもマーニも傷ついたことだろう。マーニはそれ以後、「メリー・ポピンズ」(1964)、「ムーラン」(1968) くらいで、大きな吹替の仕事は引き受けなくなった。 ちょうどその頃、マーニ・ニクソンが、ゴースト・シンガーのヴェールをはずし、スクリーンに姿を現した。「サウンド・オブ・ミュージック」(1965) の修道尼ソフィア役だった。 マーニ・ニクソンと「マイ・フェア・レディ」はご縁が深いようで、映画が公開された1964年に、ニューヨーク・シティ・オペラが上演した舞台に出演、イライザを47回演じた。それから44年後の昨2008年の「マイ・フェア・レディ」ではヒギンス教授の母役で、全米ツアーに参加しており、今なお現役である。近年では、ブロードウェイ・リバイバルの「フォリーズ」(2003)、「ナイン」(2004) 等に出演している。(続く) |
|
ベイ・シティ・ローラーズとパット・マッグリンの紙ジャケ・アルバム発売について
村岡 裕司 |
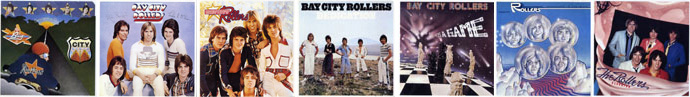
 2008年に紙ジャケ仕様で一挙リリースされたベイ・シティ・ローラーズのアルバム9タイトルに続いて、パット・マッグリンの5タイトルも紙ジャケ仕様のリリースが実現。当時のローラー・マニアはもちろんのこと、70年代ポップスの愛好家や新しくバンドのファンになった人には手に入れる絶好のチャンス到来といえるだろう。どちらも長く入手が難しかったレア盤を含んでいるのに加えて、日本で最初にリリースされた時のジャケットを忠実に再現。さらに紙ジャケ・マニアのファン心理を触発させるような帯もしっかり付いている。特にローラーズ・ファミリーのように日本で人気があったスターたちの場合、アートワークも非常に凝っていて、プラ・ケースではそのイメージを忠実に伝えない嫌いがあるが、紙ジャケの場合は当時の質感まで再現してくれるので、新鮮な感動を与えてくれる。パットの5タイトルは日本独自企画で世界初のCDリリースになることもポイントだ。 ベイ・シティ・ローラーズのアルバムは、彼らにとってセカンドとなり日本ではデビュー作となった『噂のベイ・シティ・ローラーズ』(75年 BMG JAPAN/BVCM-35528)と、続いて75年に日本リリースされたデビュー作『エジンバラの騎士』(74年 BVCM-35529)、『青春のアイドル』(75年 BVCM-35530)、イアン・ミッチェルが参加した『青春に捧げるメロディー』(76年 BVCM-35531)、脱退したイアンの後任としてパット・マッグリンが加入した時期に制作された『恋のゲーム』(77年 BVCM-35532)、『風のストレンジャー』(78年 BVCM-35533)に加えて、ローラーズ名義の『エレベーター』(79年 BVCM-35534)と『ザ・ヒーロー』(80年 BVCM-35535)の2枚を含むアリスタ時代のオリジナル・アルバム計8枚に、日本編集のベスト盤『青春の記念碑』(78年 BVCM-35536)を加えた9枚というラインナップ。最も人気があるのは、『噂のベイ・シティ・ローラーズ』から『青春のアイドル』にかけてのポップ・テイスト全開の時期だろうが、ジミー・イエナーをプロデューサーに起用した『青春に捧げるメロディー』や、ハリー・マズリンがプロデュースした『恋のゲーム』『風のストレンジャー』も、当時のアリスタを率いていたクライヴ・デイヴィス好みのAORやディスコ・テイストを取り入れた時期の作品も時代色を感じさせて味のある内容だ。ローラーズ名義の2枚は、正直あまり人気がある作品ではないが、日本を含む限られた国のリリースなど諸事情によってレア度は高い。今回の紙ジャケ化に先駆けてEU向けのリリースも実現しているものの、このチャンスに手に入れておいても損しないと思う。9タイトル中、唯一のベスト『青春の記念碑』は、以前日本でもCD化が企画されたが、契約問題等の関係でずっとペンディングになっていたアルバム。初期のキャリアを担ったノビー・クラークのレコーディングを含む非常に貴重なナンバー満載になっている。 このベイ・シティ・ローラーズとパット・マッグリンの関係はあまりに有名で、彼が参加したといわれる『恋のゲーム』からクレジットをカットされるなど苦汁なめさせられているが、日本公演にも参加した関係で我が国では絶大な人気者となった。≪伝説のバンドに悲劇のヒーローあり≫の主人公ではあるが、ビートルズのスチュワート・サトクリフのような悲しいイメージがないのは、ローラーズ脱退後、すぐに自らの音楽活動を開始して一時代を築いたからだろう。今回世界に先駆けてCD化された彼のアルバムは、パット・マッグリンとスコッティーズ名義の『パット・デビュー! あの娘はアイドル』(77年 BVCP-24153)と『デイドリーム/パット・マッグリン・バースデイ・アルバム』(78年 BVCP-24154)の2枚に、パット・マッグリン・バンドとしてリリースした『フライング・ハイ』(79年 BVCP-24155)、79年の来日公演を収録した『パット・マッグリン・ライヴ・イン・ジャパン』(79年 BVCP-24156)、新たに結成したパット・ジェームス・マッグリン&ユアーズ名義の『パトリック・ジェームス・マッグリン&ユアーズ』(82年 BVCP-24157)の5枚。レスリー・マッコーエンほど達者ではないものの、少年ならではの無垢で新鮮なヴォーカル表現は、当時多くのファンに支持されたことを改めて納得させてくれる。 皮肉にも、パットが自らのバンド活動を行った70年代後半はローラーズが先に書いたようにアリスタ的なAORやディスコ・テイストにシフトさせていた時期だが、スコッティーズ時代のパットの作品は、初期のローラーズのポップ・テイストにリンクする内容になっている。ザ・タートルズの「あの娘はアイドル」などカヴァーのセンスが優れていることや、スタッフ側の戦略もあったのだろうが、ファンが最も求めていたポップ感覚を絶妙に継承していたのが、彼の新しいキャリアにプラスになったのだろう。本家から離れた孤高のスターが、本家が確立した音楽表現の魅力をより浸透させたことは特筆すべき点である。 一方では、ヴァン・マッコイが書いた「ベイビー・アイム・ユアーズ」を取り上げているように、当時彼が傾倒していたR&B/ファンクやディスコ的な表現にも意欲的であったことも分かる。ディスコ風のAORナンバーである名曲「夢の中の恋」をフィーチュアしたディスコ風のアルバム『恋のゲーム』を送り出したローラーズもそうだが、ベイ・シティ・ローラーズ・ファミリーの音楽を語る場合、日本ではビートルズの流れを継承したポップ・テイストの部分のみで語られた嫌いはあるが、彼らのキャリアを俯瞰して語れる時代になった現在こそ、彼らの様々な音楽的チャレンジを再評価する必要があろう。 |
|
フレディ・ハバードを偲ぶ 岩浪洋三
|
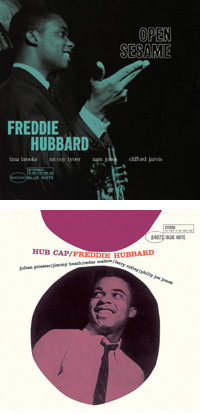 モダン・トランペッターの巨星フレディ・ハバードが昨年末に亡くなった。晩年は唇を悪くしてあまり吹かなかった。数年前にL.A.のジャズ・クラブで会ったが、ジャズ・セッション中で、多くのファンやミュージシャンがステージに上って吹くようにすすめたが、「俺は吹けない」といってついにトランペットを吹かなかった。 モダン・トランペッターの巨星フレディ・ハバードが昨年末に亡くなった。晩年は唇を悪くしてあまり吹かなかった。数年前にL.A.のジャズ・クラブで会ったが、ジャズ・セッション中で、多くのファンやミュージシャンがステージに上って吹くようにすすめたが、「俺は吹けない」といってついにトランペットを吹かなかった。彼は1938年のインディアナポリス生れで、1960〜70年代に新主流派のモード手法も取り入れた新時代のトランペッターとして大活躍した。力強いプレイと輝かしい音とアドリブで圧倒されたものだった。ブルーノートに快作が多く、『オープン・セサミ』『ハブ・キャップ』『ブレイキン・ポイント』などの吹き込みがある。60年代にリー・モーガンの代にジャズ・メッセンジャーズに加わり、3本管時代を支え、63年にこのグループで初来日し、その後度々来日した。マイルス・デイビスの代役で加わったV.S.O.P.でも大活躍したが、CTIへの『レッド・クレイ』『ファースト・ライト』などを録音したより広い層にアッピールするアルバムも悪くなかった。マイルスの後に現われたもっともすぐれたトランペッターの一人だったことは間違いない。 |
