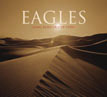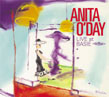![]()
| Popular ALBUM Review | |
|
「ライフタイム・ベスト/エリック・クラプトン」 |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「永遠の詩(熱狂のライヴ)〜最強盤/レッド・ツェッペリン」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPCR12781‐2) 巷ではチケットが尋常でない高値を呼んでいるという再結成公演(ペイジの骨折で延期という話に、妙に納得)やデジタル配信の開始、最新リマスターによる究極のベストの発売など、話題の尽きないツェッペリン。73年夏のNY公演を収めたライヴの名盤『永遠の詩』が、「ハートブレイカー」など6曲を新たに加えた、日本では「最強盤」なる副題の添えられたフォーマットで発売され、さらにその流れを加速することとなった。同時に5.1仕様のDVD『レッド・ツェッペリン 熱狂のライヴ』もワーナー・ホーム・ビデオから発売。こういった仕事に打ち込むペイジとは少し距離を置き、プラントがブルーグラス界の美神、アリスン・クラウスとデュオ・アルバムを出すという動きも、このバンドの性格を物語るものといえるかもしれない。(大友 博) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「エッセンシャル・ジョン・デンバー/ジョン・デンバー」 (BMG JAPAN/ BVCM-35142〜3) 70年代を代表するアーティストであり、ジブリ映画『耳をすませば』に使われたことで若い世代にもおなじみとなったフォーク・カントリーの名曲「故郷へかえりたい〜カントリー・ロード」のオリジネイターであるデンバー。没後10年企画として、多数のヒット曲を効率よく収録した2枚組ベスト盤が登場。大自然の中を吹き抜けるそよ風のような、素朴で温かい声、シンプルなアコースティック・サウンドは、今でも国境や世代を超えて多くの人の心に優しく響いて来る。また同時に70〜80年代のオリジナル・アルバム5作(BVCM-35144/35145/35146/35147〜8/35149)が紙ジャケットで限定発売。(森井 嘉浩) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「Romancing The'60s/フランキー・ヴァリ」 (Universal Motown/B0009908-02)*輸入盤 バリー・マニロウが「君の瞳に恋してる」をカヴァーしたのを受けてか当のフランキー・ヴァリも1960年代のカヴァー集を発表したが、その仕上がりの何とも粋なこと♪ボブ・ゴーディオがプロデュース、アレンジ&指揮はチャールス・カレロとアーティ・シュロック。そしてウィル・リー、ヒュー・マックラッケン、ジェフ・ミノロフら一流のミュージシャンをバックに贅沢感もたっぷりのサウンドを背景に力まずさらりとロマンティックなムードを醸し出しながら歌いこなすあたりはさすが年輪の深さ。シビレます♪「コール・ミー」「マイ・シェリー・アモール」「マイ・ガール/グルーヴィン(メドレー)」「サニー」など相性の良い選曲で全13曲。御年70歳!(上柴 とおる) |
|
| Popular ALBUM Review | |
 |
「IT’S CHRISTMAS,OF COURSE/ダーレン・ラヴ」 (Shout !Factory/826663-10569)*輸入盤 毎年恒例のごとく出されるレギュラーのコンピレーション盤はさておき、時に思わぬアーティストから届けられるスペシャルなクリスマス・アルバムは本当に楽しみ♪1960年代のフィル・スペクターのXマス・アルバム(今や幻の名盤)でも活躍していたダーレン・ラヴの新譜は即購入。バンド編成でトム・ペティ、プリテンダーズ、ビリー・スクワイアー、ザ・バンド、ジョン&ヨーコ(シシィ・ヒューストン参加で「ハッピー・クリスマス」)やXTC(!)などロック系のXマス・ソングを中心に歌い上げるが、個人的に大好きなN.R.B.Q.の知る人ぞ知る名曲「クリスマス・ウィッシュ」には参った!まさに興味津々、意表をつく(?)ような新しいXマス盤の登場だ。(上柴 とおる) |
| Popular ALBUM Review | |
|
「コード・ブルー/シュガー・ブルー」(BSMF RECORDS/BSFM-2065) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「レット・ゴー/ケリ・ノーブル」(ビクターエンタテインメント/VICP-63922) う、この感じ、懐かしい。けど、少し暗め。間違いなく70年代女性シンガー/ソングライターのマニアの女性とすぐわかる。とバイオを読めばジョニ・ミッチェルのファンということだ。3年前のデビュー・アルバム『フィアレス』はEMIから、アリフ・マーディンのプロデュースといえば、ピンと来る。そう、ノラ・ジョーンズ体制だ。「レコード・コレターズ」誌に書かせていただいたが、ノラの1枚目は、マリア・マルダーをひな形にしている可能性が強いと思う。こちらはジョニということだ。現在の女性シンガーの隆盛は、70年代の優れたシンガー/ソングライターに根を求めていると思える。20代の娘ということは、MTVが流行りだしたころ、生まれたということで、70年代には影も形もない。今回は、EMIから移籍しての盤で、アリフはかかわっていない。テキサス出身、デトロイト育ちの26歳。メロディ、詞とも優秀で今後が楽しみ。後は抜けるような明るさが欲しい。ジョニは暗めとはいえ、天空がバリっと抜けていた。(サエキ けんぞう) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ワン・チャンス/ポール・ポッツ」(BMG JAPAN/BVCP-21568) イギリスで初登場1位に輝くなど、各国で大ヒットしているクラシカル・クロスオーヴァー系の新人のデビュー作。イギリスの人気オーディション番組でチャンピオンになった無名の30代男で、イル・ディーヴォを送り出したサイモン・カーウェルがバックアップしていることなど、話題にも事欠かないが、オペラからミュージカル、ポップス、ロック、民謡を、見事な熱唱で聴かせる。それなりの教育や経験を持つ人だが、音楽学校の優等生的な表現ではなく、トラック運転手から認められたマリオ・ランザのような、昔の歌手に通じる生活感があるのは、サクセス・ストーリーから来る先入観だけではないと思う。(村岡 裕司) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ヘッドストロング/アシュレイ・ティスデイル」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPCR-12738) アメリカで高視聴率を記録したディズニー・チャンネルの『ハイスクール・ミュージカル』のキャストが映画やレコーディングに進出して大活躍しているが、彼女も同作品でブレイクした人気スターの一人。このデビュー作では、R&B/ヒップホップからバラードまで、幅広いレパートリーを達者に歌いこなしている。新作の前までのブリトニーにアプローチに近いが、ヴォーカルはオリビア・ニュートン・ジョンにリンクするお嬢様風。ディズニーが送り出すアイドルは相変わらずポップスのメインストリームである。(村岡 裕司) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ディランを唄う/和久井光司」(ソニー・ミュージック/MHCL1234) ボブ・ディランのカヴァー作品は、全世界で2万曲以上あり、その中には日本語で歌った作品もいくつかある。しかし、日本語によるカヴァーだけを集めて1枚のアルバムを発表したのは今回の和久井光司が初めてで、その結果は成功だ。ディランが公認した日本語詞は、原曲の内容を忠実に訳した歌から、原曲とはまったくちがった新たな歌詞をつけたものまでさまざまだが、どの歌も聴き手に訴えかける力強さにあふれている。やはり日本語はありがたい。さらに、この作品集の魅力は、ディランのカヴァーとなるとフォーク時代の作品を歌うケースが多い中でが、和久井が1963年の代表曲「風に吹かれて」から、意表をつかれる2006年の「約束を交わすとき」まで、選曲がじつに幅広い時代におよんでいることだ。とくに「ブラインド・ウィリー・マクテル」は見事。この1曲だけ でも聞く価値はある。また、ジャケットに使われた浦沢直樹の絵も、ディラン・ファンの心をくすぐるディテールが描かれている。(菅野 ヘッケル) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「Apple of our eye りんごの子守唄(白盤)/VA」 (ビデオアーツ・ミュージック/B000WC71Z6) ビートルズ解散後に、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターが歌ったソロ時代の名曲を子守唄のアレンジでカヴァーした作品集。女性ヴォーカル(赤盤)と男性ヴォーカル(青盤)で聞かせた前2作に続く第3弾として発売。今回はデュエットが中心で、「ラヴ」を小池みつ子+細野晴臣、「イマジン」をYO-KING+土岐麻子、「ルック・アット・ミー」を湯川潮音+曽我部恵一が歌い、インストゥルメンタルの「ジャンク」を含め全13曲収録。子どもたちだけではなく、大人たちの心も癒してくれるだろう。(広田 寛治) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「COVER ALL YO!/山崎まさよし」(ユニバーサルミュージック/UPCH-20051) 山崎まさよしが邦楽カヴァー集『COVER ALL HO!』とこの洋楽カヴァー集を同時発売。こちらの洋楽集では、ビートルズをはじめ、スティング、スティーヴィー・ワンダー、エルトン・ジョン、モンキーズなどの10曲を山崎風に料理している。ビートルズの「オール・マイ・ラヴィング」は、来日したポール・マッカートニーと会見したときに目の前で披露したという曲で、今回は「シェフの家ごはん」風に自宅録音。全編を通じてセンスあふれる仕上がりで、洋楽ファンにも心地よい。(広田 寛) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ロペ・カイ/エネイダ・マルタ」(キングレコード/KICP8084) 今年「世界の女神<ディーヴァ>たち」というシリーズを監修させていただいた。 英語圏ではなく、世界各地で活躍するトップ・クラスの女性シンガー20名を紹介する シリーズだ。日本ではこれまであまり聞くことのできなかった地域の歌手がほとんどだが、音楽は親しみやすいものばかりである。その中でこの人は西アフリカのギニア・ビサウ出身のポップ・シンガー。いまはかつての宗主国ポルトガルのリスボンを拠点に活動しているようで、このアルバムの音楽にも西アフリカのリズムとヨーロッパ的なポップな感覚が同居している。哀愁味のあるメロディも陽性の歌声でうたわれるから、べたつかない。遠赤外線のような暖房効果のある音楽だ。(北中 正和) なお、このシリーズの詳細は以下の小生のサイトでごらんいただけます。 →http://homepage3.nifty.com/~wabisabiland/diva.html |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「アンコール/アルトゥール・ヴェロカイ」(ヴィレッジ・アゲイン/VIA-0064) ギタリスト、作曲家、編曲家と多才なアルトゥール・ヴェロカイの35年ぶりの新作が登場した。一聴するだけでなつかしさがこみ上げてくるブラジリアン・サウンドだ。それもそのはずでガル・コスタ、ジョルジ・ベン、エリゼッチ・カルドーゾ、MPB4、カルテート・エン・シー、イヴァン・リンスと、きら星のごときスターたちの編曲を、長年手がけてきた人なのだ。特にストリングス・アレンジは耳なじみの方もきっと多いことだろう。アルバムは全12曲すべてアルトゥーロのオリジナル。イヴァン・リンスやアジムスを迎えてのトラックも魅力だが、マルシオ・ロット、クラリッセ・グローヴァのふたりをフィーチュアしたトラックが、ガルやブラジル66などにも一脈通じるポップ感を届けてくれる。インストゥルメンタル・ナンバーは時にジャズやファンクのように、時に映画音楽のような広がりを聴かせる。(三塚 博) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「アダージョ〜世界はゆっくりと開けてゆく…/宮野弘紀 ルーラ・ガルヴォン・デュオ」(スタジオNana/STN-2701) 「マンハッタン・スカイライン/宮野弘紀」(ユニバーサルミュージック/DCT-1921) アコースティック・ギタリストとして30年以上、国内海外で活動を続けている宮野弘紀のアルバムが相次いで登場した。「アダージョ」は2006年から2007年にかけてリオで録音された最新作。ブラジルのギタリスト、ルーラ・ガルヴォンとのデュオ・アルバムだ。日本ではなじみの薄い名前だが実はブラジルでは多くの作品に参加し、たくさんのミュージシャンから信頼され尊敬されているギターの達人だ。宮野は10年以上も前からルーラの品性溢れるサウンドに惹かれていたという。自身の楽曲をルーラなら豊かに広げてくれるに違いないという長年の強い思いが今回の作品へとつながった。ふたりの息の合ったプレイ、間合いやゆったり感は、聞く者を映像の世界へと導いてくれる、そんな仕上がりだ。もう1枚が「マンハッタン・スカイライン」。宮野のデビュー作品。ジャズ・プロデューサーで評論家の児山紀芳に見いだされ、1980年にニューヨークで録音されたもので、発表当時大いに注目を集めた。マイルス・デイビスなどを手がけるテオ・マセロをプロデューサーに迎え、マーカス・ミラー(b)、ジョージ・ヤング(ts)、デイブ・ヴァレンティン(fl)、ジェフ・ミロノフ(g)、ホルへ・ダルト(p)、川崎 燎(g-synthe)などニューヨークのトップ・ミュージシャンがこぞって参加している。フュージョン・タイプのアルバムで宮野のオリジナル6曲に加えて、アール・クルー、川崎燎、テオ・マセロが曲を提供している。何度か再発売の計画もあったようだが、発表から27年、今回のアルバムが初CD化だ。(三塚 博) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「イン・ザ・ムード〜プレイズ・グレン・ミラー/マンハッタン・ジャズ・オーケストラ」 (BIRDS RECORDS/ XODJ-1003) グレン・ミラーのナンバーはスイング・ビッグ・バンドの主要曲ともなっているが、本作はモダン・ビッグ・バンドの雄MJOが、リーダー、デビッド・マシューズの新編曲で演奏しているのが、聴きものだ。「真珠の首飾り」「タキシード・ジャンクション」「イン・ザ・ムード」などがひとひねりした編曲で、新鮮なミラー・ナンバーとして甦っている。ミラー曲の魅力を再発見することのできた快作だ。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「恋に過ごせし宵/カラブリア・フォーティ」(キングレコード/KICJ-526) 滑らかで甘く、かつ知的な歌声だ。カラブリアはニューヨークの音楽一家の出身。クラシックを両親が奏で、ジャズ・クラブへも行く生活の中で音楽センスが育った。エラ、ペギー・リー、ガーランドからサミーに至る幅広い歌手から影響を受けた。これがデビュー・アルバムとは思えないほど完成度が高い。言葉の表現が美しく、すんなり歌って気持ちよい。バックもすっきり。テーマに沿って構成するのが好みとかで、恋人との長夜を描く選曲がされているのでロマンティック仕立て。「ドゥ・イット・アゲイン」はじめ味わいも濃やかで、アドリブを多用した新鮮な解釈の「クローズ・ユア・アイズ」もうまい。有名歌手、作曲家たちが絶賛するのもうなずける。(鈴木 道子) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「Little Tiny/矢野沙織」(コロムビアミュージックエンタテインメント/COCB 53685) いま日本でライヴ・ハウスなどで活躍している、ジャズの女性のアルトサックス奏者は10人ほどいるが、その中で人気抜群で、実力者でもあるのが矢野沙織だ。高校生でデビューし、今年21歳になるが、本作は最新のニューヨーク録音で、成長著しいものがある。アルトが美しく、まろやかで力強く鳴っており、音が魅力的だ。今回はオルガンの名手ロニー・スミスとの共演も注目される。また選曲がすばらしい。ホレス・シルバーの神秘的な「スプリット・キック」、マイルスの「バプリシティ」、パーカーの「シー・ロート」「K.C.ブルース」が注目されるし、思い切りブローした熱い演奏もあり、「クロース・トゥ・ユー」といったバラードもよく、表現も大人っぽくなってきた。また美空ひばりの歌う「A列車で行こう」にかぶせた演奏も面白い試みで楽しめる。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス/グレース・マーヤ」 (ヴィレッジミュージック/VRCL-11005) もともと弾き語りの日本人だが、今回はソウルとラテン・ミュージックに挑戦し、みごとに変身を遂げている。ブラス、サックス、パーカッションを加えたサウンドもリッチで躍動的であり、日本人歌手のアルバムとしてはユニークで個性的で楽しい。「ソウル・シャドウズ」「フィール・ライク・メイキン・ラブ」「フェリシダード」「ベサメ・ムーチョ」などを歌っており、そのエキゾティックな雰囲気をたっぷりと味わうことができた。笹路正徳(key)、カルロス菅野(per)、中川英二郎(tb)、小沼ようすけ(g)らが加わっている。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ポートレーツ/三槻直子」 (What’s New Records/WNCS-5107) 人気シンガー、三槻直子の3作目。恵比寿ビールの黒ビールやエステのTBCのTV-CMなどでお茶の間に親しまれている三槻だが、実に4年半ぶりのリリースである。本作ではバックのメンバーが前2作から大きく変わり、清水絵理子(p)、高瀬裕(b)、井川晃(ds)という若いメンバーを起用している。3人とも実力があり、音楽性も高い。満を持しての作品だけに、深みのあるジャズ・ボーカルの魅力を湛えた作品が誕生した。どの曲も心に響く美しさがある。スタンダードの数々は、新鮮なアレンジの解釈を得ていっそう伸びやかである。みずみずしい情感とほのかな色香をたたえた三槻の声は、心地好い。「クローズ・ユア・アイズ」などは、難しい5拍子に挑戦している。(高木 信哉) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「トランジェントシティー/井上オサム」(T-TOC RECORDS/XQDN-1008) 活況を呈すJ-JAZZシーンに、井上オサム(ts)という新たな才能が現われた。本作は、井上のデビュー作。井上は、北海道大学のジャズ研の出身である。当時よく演奏した仲間が井上祐一だ。1997年から3年間、ニューヨークに暮らし、徹底的にジャズを学んだ。全曲が、井上オサムのオリジナルである。標題曲は、東京の街をイメージして書いた曲。5拍子のファンクが基本になっていり、4拍子〜3拍子と変わっていくが、全体を流れるグルーブ感が格好いい。井上のテナーはアイデアに満ちていて、ジョー・ヘンダーソンや山口真文を彷彿とさせる音がする。「ドミノ」は、唐沢寧のエレピ“ローズ”と井上のテナーが絶妙なマッチングをみせる美しい曲。素晴らしいデビュー作と感心する。(高木 信哉) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「恋をしましょう/アニタ・オデイ」(ラッツパック・レコード/RPCJ-7002) 1978年にアニタ・オデイがドワイト・デッカーソンのトリオをバックに行った岩手のジャズ喫茶≪ベイシー≫でのライヴ録音。体調も良く、気分も乗っていたのか、リラックスした素晴らしいアニタの歌が聞ける。「ライク・サムワン・イン・ラヴ」や「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」では珍しくヴァースから歌っている。彼女のライヴ録音は、幾つもあるが中でも一・二を争う出来だろう。最後の方では『真夏の夜のジャズ』で歌った「二人でお茶を」をそっくりに再演して聴衆を喜ばせている。(高田 敬三) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「クロスロード・ギター・フェスティヴァル/エリック・クラプトン」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPBR-90680〜1) 今年7月にシカゴで開催された≪クロスロード・ギター・フェスVOL.2≫のDVDが早くも完成した。11時間強のイベントを2枚組にまとめているのだが、現場にいた者として、大事なパートはほぼ収められているなという印象を受けた(大好きなアリスン・クラウスは契約の関係なのか、収められていない。残念)。ハイライトはやはり、クラプトン・バンドにスティーヴ・ウインウッドが参加してパートだろう。ブラインド・フェイスからも3曲が取り上げられているが、その時「ひょっとしたら」と思ったことが、2月にニューヨークで現実となる。クラプトンの「家族を大切にしながら音楽にもきちんと打ち込む毎日」はまだまだつづいていきそうだ。(大友 博) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「ニューポート・フォーク・フェスティバル 1963-1965/ボブ・ディラン」 (ソニー・ミュージック/SIBP97) 60年代のディランの映像はあまり多く存在してないので、このDVDは貴重だ。ディランが出演したニューポート・フォーク・フェスティバルの映像を断片的に収録した作品はあったが、このDVDは撮影されたディランの映像のすべてをカットなしで収録している。しかも、ドキュメント作品にありがちな説明的なナレーションを入れずに、ステージで歌うディランの映像にすべてを語らせる手法をとっているので、ニューポートの会場にいるような気分にさせられる。63年の初々しい少年の面影を持つデビューまもないディランから、翌64年のフォークのプリンスとしてフェスティバルの中心的スターに成長したディラン、さらに65年のいわゆる“ニューポート事件”として知られるロック・バンドをバックに歌った問題のディランまで、80分間のモノクロ映像でディランの3年間の成長と変化の過程を見事に伝えてくれる。ディラン・ファンにはたまらない作品だ。また、ボーナス映像として監督のインタビューも収録されている。(菅野 ヘッケル) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「アンシーン・ビートルズ」(ソニー・ミュージック/SIBP-91) ビートルズがレコード・デビューを果たしてからライヴ活動を中止するまでのドキュメンタリー作品。ビートルズ初期の歴史を語るに不可欠なトニー・バーロウをはじめ、リバプール・ハンブルク時代を知るアラン・ウイリアムズ、ツアーなどに同行した経験を持つラリー・ケイン、ジョンのキリスト発言のきっかけとなった記事を執筆したモーリン・クリーブらも登場して興味深いエピソードを披露。サンフランシスコのキャンドルスティック・パークで行なわれたビートルズ最後のライヴを観客が撮影した短い映像や、日本ではあまり知られていなかったニュース映像や写真なども使われている。2007年にイギリスで制作され発売された作品で、時々登場するこの手のビートルズもののなかでは秀逸な作品に仕上がっている。(広田 寛治) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「プラグ・ミー・イン〜コレクターズ・エディション・3DVD・セット〜 AC/DC」 (ソニー・ミュージック/SIBP-100〜2) 1970年代から活動しているAC/DC、オーストラリア出身の彼らはもちろん現在も着実に活躍している。実にエネルギッシュなロック・バンド、81年の初来日公演(日本青年館)の凄さを想い出す。そんな彼らのヒストリー映像が3枚のディスクにぎっしりと収録された。ファンにとってはたまらない内容。もちろん東京公演も収録されているのだ。また、2003年にストーンズにジョイントした「ロック・ミー・ベイビー」もこの作品集で初めてオフィシャル化。ストーンズ・ファンにとっても見逃せない。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「チャック・ベリー ヘイル!ヘイル!ロックンロール コレクターズ・エディション」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPBR-90661〜4) ロックンロール創設期の重要ミュージシャンとして忘れることの出来ないチャック・ベリーの60歳記念コンサートの模様がDVD化されたが、その通常盤に加えて4枚組コレクターズ・エディションが発売される。キース・リチャーズのプロデュースで多くのゲストも参加してのコンサートも大成功。その模様ももちろん必見だが、同時に≪ディスク-3≫「歴史の目撃者/チャック・ベリー、リトル・リチャード、ボ・ディドリー」「焼けたスクラップブック/チャック・ベリー&ロビー・ロバートソン」はまさに生のロックロール歴史証言としてひとりでも多くの音楽ファンにしっかり見て欲しいのだ。(高見 展) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「ライヴ・アット・モンタレー/ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス」 (ユニバーサルミュージック/UIBO-1135) 1967年6月18日に開催された歴史的音楽祭、モンタレー・ポップ・フェスティバルでのジミ・ヘンドリックスのステージがいっきに楽しめる。このライヴを足がかりにしてジミはアメリカで大成功、その名を全世界へと広めた。イントロで多くの関係者が当時を振り返り、そして熱狂的なパフォーマンスへと続く。紹介はブライアン・ジョーンズだ。「ヘイ・ジョー」「紫の煙」「ワイルド・シング」・・。60年代後半のロックの姿をダイレクトに伝えてくれる。同時にCD『ライヴ・アット・モンタレー』(ユニバーサルミュージック/UICY1396)もリリースされた。こちらではDVD未収録の「キャン・ユー・シー・ミー」を聴くことができる。(高見 展) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「ロニー〜MODSとROCKが恋した男〜」(ハピネット/HMBR-1054) ロニー・レインが他界して10年が経つ。スモール・フェイセズ、フェイセズのメンバーとして活躍。その後はスリム・チャンスも活動させたロニー、旧友、イアン・マクレガンと来日したこともある。でもその時は病状がだいぶ進行していた・・。この作品はロニー・レインのドキュメンタリー。彼の音楽人生をしっかりと残してくれている。イアン、エリック・クラプトンほか多くの友人達が想い出も語っている。ブリティッシュ・ロック史の一頁を垣間見るようだ。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular BOOK Review | |
| 「ニューオーリンズ・ミュージック・ガイド・ブック/監修:文屋章 吉田淳」 (ブルース・インター・アクションズ) アメリカのポピュラー・ミュージックを語る上でニューオーリンズを忘れることは出来ない。ジャズ、ブルース、リズム&ブルース、そしてロック。まさにニューオーリンズは音楽の都だ。実際、同地を訪れると音楽であふれている。そんなニューオーリンズ音楽をとても丁寧にガイドしてくれる素晴らしい内容。700枚以上のアルバムからアーティスト、音楽用語の紹介。ニューオーリンズの世界をしっかり、そして楽しく味わえるのだ。ブルース・ファンはもちろんだが、若いロック・ファンにもじっくり触れて欲しい・・・。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular BOOK Review | |
| 「父から子に伝える名ロック100/立川直樹」(祥伝社) 筆者から見れば、約10年、人生と業界の大先輩である著者が、タイトル通りのコンセプトで記した内容には、驚くほど生まれた時代による気持ちのズレがない。アルバム選ではなく、名曲を100曲選んだところが、本著のユニークなところ。クロスビー・スティルス&ナッシュは「マラケッシュ・エクスプレス」が選ばれていることなど「そうだよな〜」とか心で相づちを打つ。この世代差を感じさせない感慨は、ロックのパワーからもたらされた偉大なる財産なのではないだろうか?ジャズではなかなか、こういうわけにはいかないと思う(ジャズの先生方、失礼)。題通り、なんとか子の世代にも伝えたい。ピンク・フロイド「シャイン・オン・ユー・クレイジー・ダイヤモンド」を外国俳優と合唱した思い出など、著者のさりげない日常のエピソードが楽しい。ほとんどの曲がおなじみだが「霧のベイカー街」(ジェリー・ラファティー)のようなレア曲も含まれている。(サエキけんぞう) |
|
| Popular CONCERT Review | |
|
|
「3グレート・アメリカン・ボイセズ」 11月10日 さいたまスーパーアリーナ アメリカ・ポピュラー音楽を代表する3人の女性シンガーが競演するスペシャル・イベント。トップ・バッターはブラック・アイド・ピーズの紅一点で、昨年ソロ・デビューも果たしたファーギーだ。へそ出しミニスカの衣装で登場すると、アリーナの観客はいきなり総立ち。バラード「ファイナリー」ではキーボードのみの伴奏で、歌唱力の高さを見せてくれた。SSWの最高峰であるキャロル・キングはまさに感動的なステージ。最新映像作を再現したシンプルな編成で、名曲の数々を弾き歌う。その姿に自分自身の音楽ファン歴が重なり、涙が止まらなかった。絶唱と言うべき「ノー・モア・ドラマ」、メッセージ性を打ち出した「ワン」等が圧巻のメアリー・J・ブライジは、女王の名に恥じないパフォーマンス。最後に3人が揃って2曲を披露。終わってみれば人選にも納得の、夢の共演であった。 (杉田 宏樹) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「第19回カントリーゴールド」 10月21日 ASPECTA(グリーンピア南阿蘇) 熊本在住のカントリー・シンガー、チャーリー永谷氏が主宰する国際フェスティバル。第19回目の今回は、’90年代を代表するトラディショナリスト:マーク・チェスナットをヘッドライナーに、ロックからヒップホップまで取り込んだダンサブルなサウンドが売りの、パワフルで魅力的な新人女性デュオ:ボムシェル、イキのいい若手カントリー・ロック・バンド:ロスト・トレイラーズ、結成からわずか6年でブルーグラス界のトップに登りつめたファミリー・バンド:チェリーホームズを迎え、秋晴れ(今年は例年より冷え込んだ!)の阿蘇山麓に集まった大勢の観客を魅了した。音楽ファンはもちろん、家族連れや友人同士でのピクニック気分でも楽しめるところが、このフェスティバルの特徴。日本全国から年1回、再会を楽しみに集まる人も多い。いよいよ20年目となる来年も、期待したい。(森井 嘉浩) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「JAZZ TODAY 2007」 10月15日〜18日 六本木/スイートベイジル139 現代日本のジャズの底力を知ることができる素晴らしいコンサート・シリーズが今年も盛大に開催された。10月15日には渡辺香津美(スペシャル・ゲスト吉田美奈子)、16日には水谷浩章(ベース)のプロデュースによる“リスク・ファクター&フォノライト・アンサンブル”と“フォノライト”、17日にはBOZOと南博トリオ・ウィズ・弦楽四重奏、18日には中島ノブユキ・エテパルマ・アンサンブルが登場。僕は16日と17日に行き、両日とも大いに興奮させられたが、ことに16日は圧巻だった。水谷の指先一つでハーモニーが繊細にも獰猛にも変化する。その上で流れるように響き渡るMiyaのフルートや中牟礼貞則のギター。ジャズ・アンサンブルの美に魅了されたステージだった。 (原田 和典) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「ギンザ・インターナショナル・ジャズ・フェスティバル 2007」 11月3日〜4日 シャネルネクサスホールほか 今年で3回目を迎えたジャズ祭。アメリカ、イタリア、ベルギーからの来日アーティストを含む14組が、東京・銀座エリアのホールとショップで繰り広げるフリー・コンサートだ。有名ファッション・ブランドのビルが続々と生まれている銀座で、各社が共同主催するこの祭典は、すでにタウン型ジャズ祭の新しい成功例となっている。今回、特に印象的なステージだったのが、若手黒人ビブラフォン奏者ウォーレン・ウルフと、トランペッターのフラビオ・ボルトロ。ウルフはミルト・ジャクソン譲りの正統的な奏法をベースに、現代的なセンスを加味したスタイルで、テクニシャンぶりをアピールした。カルテットを率いたボルトロは切れ味鋭い高速プレイで魅了。このような現場から広くジャズの素晴らしさが伝わるとの感を深くしたのだった。(杉田 宏樹) 写真:(C)GIJF2007 PHOTO: TCB |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「KAIBUTSU LIVES」 10月1日 荻窪/杉並公会堂小ホール セロニアス・モンクやアルバート・アイラーとの共演で知られる伝説のベーシスト、ヘンリー・グライムス。一時は死亡説すら流れていた彼が再び楽器を手に取り、ニューヨークで活動を始めてから5年以上が経つ。そのグライムスがソニー・ロリンズの初来日に同行して以来、44年ぶりに日本の土を踏んだ。共演者は原田依幸(ピアノ 日本)、トリスタン・ホンジンガー(チェロ 米国→オランダ)、ルイス・モホロ(ドラムス 南アフリカ)等。ほとんど初顔合わせの一発勝負だったと思われるが、ベースとヴァイオリンを交互に使い分けるグライムスの迫力は、さすがというしかないもの。ロウアー・マンハッタンの空気が杉並を覆う、不思議なひとときを味わった。(原田 和典) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「ヤドランカ・音色・コンサート」 11月7日 品川教会 旧ユーゴのサラエボ出身で、日本滞在中に祖国を失い、日本を拠点に今や世界を舞台に高い評価を受けて活躍しているヤドランカのコンサートが、今月7日、品川教会で行われた。こんなに安らぎに満ち、ほっと心が温まることはついぞない。7枚目の新作『音色 おといろ』(オーマガトキ/OMCX-1183)を出したばかり。子守唄をテーマにしたというだけに、アルバムはやや平坦で優しいが、ステージは巧みな日本語で、くだけたおしゃべりを交え、民族楽器やギター、パーカッションも入り、シンプルな中に暖かさと深みのある歌を聞かせた。夢だけが頼りといった「予感」に始まり、サラエボ地方の民謡や各国の子守唄、俳句、自然はそのままがよいという環境保護を歌うなど、円熟味と人柄がにじみ出て、心の通い合うコンサートだった。(鈴木 道子) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「みんなでボブ・ディランを歌う日〜初台で風に吹かれて」 11月15日 初台/THE DOORS 不思議な3時間半だった。出演者の年齢は20代から60代まで広がっていたが、ディランの音楽を愛する気持ちは全員が共有していたようだ。ただ、その表現はさまざまだったが。なつかしいフーテナニーの夜を思い出させてくれた若い女性二人組のTHE DUET(ザ・デュエット)、強いメッセージが伝わってきた中川五郎、カントリーの楽しさを味合わせてくれた麻田浩、最近のディランを連想させるロック・サウンドで楽しませてくれた和久井光司、孤高のステージを見せてくれた南正人と、じつにバラエティ豊かで、ディランのローリング・サンダー・レヴューを連想させるような一夜だった。また、ザ・デュエットが日本語で「アバンダンド・ラヴ」を歌ったのに驚かされ、和久井が日本語で「ブラインド・ウィリー・マクテル」を歌ったときには、あらためて日本語のありがたさを感じた。もちろんコンサートの最後は約束どおり出演者全員がステージに登場し、「アイ・シャル・ビ・リリースト」とレゲエ風にアレンジされた「風に吹かれて」を歌った。ただ、あえて注文をつけるなら、今後こうしたコンサートがふたたびどこかで開かれる場合は、日本語で歌ってほしいことと、全曲ディランの作品に限ってほしいということだ。(菅野 ヘッケル) |
| Popular INFORMATION | |
 |
「ナンシー・ハロウを聴く会」 キャンディド・レーベルの『Wild Women Don't Have The Blues』やジョン・ルイスとの共演アルバムで有名なベテラン・ジャズ・シンガー、ナンシー・ハロウの一晩だけの≪聴く会≫が開催される。どなたでも参加OK! 会場:高田馬場「Cafe Cotton Club」 日時:2007年12月9日(日)開場20:00 開演20:30 参加費:4500円プラス飲食ミニマム・オーダー2000円 予約:03−3207−3369 |
| Classic DVD Review | |
| 「ミッシャ・マイスキー/ハイドン&シューマン:チェロ協奏曲集」(ユニバーサル ミュージック/UCBG-1233) 1985年にシューマンがバーンスタイン、ウィーン・フィルとのライヴ、そして1987年にハイドンがマイスキー自身の弾き振りでのビデオ用に収録された映像だが、日本では今回が初発売である。最初に入っているのがハイドン、そして最後がシューマンだが、この2種類の映像を見ると実に興味深い差があるのだ。ハイドンを振りながら演奏するマイスキーは天衣無縫とも言える仕草を見せる。弾き振りをはじめてから間もないのだろう、極端に言って振りはアマチュアの域を出ていない。しかし本職のチェロは実に楽しそうで、変な例えだが、先生のいない教室で番長の生徒が他の生徒を従えて、自由奔放に振る舞っているかのようだ。伴奏をしているウィーン・シンフォニカーの選抜メンバーの上手さと相まってこれは絶品。一方この2年前のライヴはと言うと、緊張感の中にも歌が溢れる極上のシューマンで、マイスキーよりもバーンスタインの偉大さが画面に映し出されているようだ。(廣兼 正明) |
|
| Classic BOOK Review | |
| 「進化するモーツァルト」樋口隆一編著 春秋社刊 〈モーツァルト生誕250年〉は彼の音楽をいっそう身近なものにしたが、未来に種を蒔くことにもなった。本書はその収穫の一つで、樋口隆一(本会会員)の呼びかけで開催された明治学院大学での国際シンポジウム「モーツァルトの大衆性」の内容を再構成したもの。主な内容は「2006年の視点から見たモーツァルト受容史」(G.グルーバー)、「音楽祭創設以前のザルツブルクのモーツァルト受容」(M.H.シュミット)、「モーツァルトとウィーンの聴衆」(O.ビーバ)、「文学におけるモーツァルト像」(O.パナーグル)、「日本のモーツァルト受容」(海老澤敏)、「モーツァルトとメンデルスゾーン」(星野宏美)、「リストがとらえたモーツァルト像」(福田弥)、「20世紀ヨーロッパ音楽におけるモーツァルト受容」(M.シュミット)、「ラノワ・コレクションのモーツァルト資料」(西川尚生)、「日本のモーツァルト伝承」(樋口隆一)。広い視野から天才作曲家を多角的に捉えた優れた論考で、ぜひ一読をお勧めしたい。(青澤 唯夫) |
|
| Classic CONCERT Review | |

|
「モーツアルトへのオマージュ」10月5日 東京/イタリア文化会館 アニエッリホール タイトルだけをみるとモーツアルトの曲を特集したプログラムのようにも思えてしまうが、実際にとりあげられたモーツアルト・ナンバーは「寂しい森の中で」、「ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いた時」のみ。彼の影響を受けた20世紀の作曲家の楽曲がプログラムの中枢をなしていた。クリスティーナ・パストレッロのソプラノはささやきから叫びまで自由自在、クラウディア・ロンデッリ(ピアノ)もクラスターを連続させてアグレッシヴに迫った。当夜のMCも務めた作曲家ダヴィド・マッグリも自作「ソプラノとハープのための2曲」を提供。ハープのパートをピアノに適応させ、奔放に鍵盤をまさぐるクラウディアは聴覚的にも視覚的にも大変な迫力だった。(原田 和典) |
| Classic CONCERT Review | |

|
「ベルリン国立歌劇場《トリスタンとイゾルデ》」10月8日 神奈川県民ホール ベルリン国立歌劇場が音楽監督のダニエル・バレンボイムに率いられて、5年振りに来日した。「トリスタンとイゾルデ」の初日を観た。いわゆる<ワーグナー歌い>の錚々たる顔ぶれをそろえたが、マルケ王を演じたルネ・パペが傑出した存在を示した。王でありながら、実らない愛の悲しみを底光りのするバスに託して歌い、悠揚迫らざる所作も貫禄を備えている。イゾルデ役を得意中の得意とするワルトラウト・マイヤーも、感情の起伏をストレートにソプラノで表現して、豊かな経験の片鱗をみせた。この2人のスター歌手を相手に、トリスタンのクリスティアン・フランツは悲劇の主人公に果敢に挑戦して、大役を果たした。これらの主役たちを向こうに回して、ブランゲーネに起用されたミシェル・デ・ヤングも目覚しく活躍した。むしろヤングの目立たない熱演が、主役たちにスポットライトを与え、引き立たせたとみたい。バレンボイムの絶妙なタクトとハーリー・クプファーの精緻な演出が、歌手陣をしっかり支えた。(椨 泰幸) 〈Photo:長谷川清徳〉 |
| Classic CONCERT Review | |

|
「群馬交響楽団 東京公演」10月19日 東京芸術劇場大ホール なんどか群馬交響楽団の演奏を聴く機会があった。聞くたびに上達しているので驚きだ。高関健音楽監督と楽団員とも慣れ親しんだ関係でしっくりした指揮による演奏だった。「交響曲第90番 ハ長調」(ハイドン)は装飾音符も古典奏法のアッツポジァトウーラに統一され見事だった。この日の圧巻だったのは「クラリネット協奏曲「カビィラ」(天界の鳥)」(西村朗)であった。独奏は名手カール・ライスターを迎え素晴らしい演奏だった。カビィラとは仏教界における極楽浄土にすむ鳥のことだが、まさに人の魂を揺さぶるかのように、大空を舞う姿を彷彿させるがことき演奏だつた。ライスターにしては熱演であった。「管弦楽のための協奏曲Sz.116」(バルトーク)はコントラバス・トロンボーンまで使う大曲でかつ難解な作品だったが、真摯な態度でとりくみ快演であった。(斎藤 好司) |
| Classic CONCERT Review | |

|
「ベルリン国立歌劇場《モーゼとアロン》」10月20日 東京文化会館 12音技法を創設し、現代音楽に強烈なインパクトを与えたアルノルト・シェーンベルクのオペラと聞けば、難解と思われがちであるが、バレンボイム(指揮)、ペーター・ムスバッハ(演出)のがっちりしたスクラムで、核心に迫る出色の出来栄えとなった。 出典は旧約聖書で、台本も作曲者が執筆した。神託を受けたモーゼ(ジークフリート・フォーゲル)とアロン(トーマス・モザー)が、ファラオの圧政にあえぐ民衆をエジプトから約束された地へ率いて行くという物語である。モーゼはシュプレッヒ・シュティンメ(歌うように話す)によって重々しく想念の至上を説くのに対して、テノールのアロンは信仰の拠り所となる形象も民衆の教化に必要と歌い上げる。対立した2人のやりとりには緊迫感があり、救済を求める合唱のハーモニーも悲痛な響きが込められていた。出演者は黒ずくめのスーツにネクタイ、舞台の建物もビルを思わせて現代風であったが、時折不協和音も混じる音楽とうまく溶け合って、間然する所がない。いわゆる新演出のケレン味はいささかもなく、オペラの魅力を堪能した。(椨 泰幸) 〈Photo:長谷川清徳〉 |
| Classic CONCERT Review | |

|
「イ・ムジチ合奏団」10月27日 フェスティバルホール 季節感の豊かな日本で、ヴィヴァルディ「四季」は世代を超えて絶大な人気を誇っている。1952年にローまで結成されたこの楽団は、いち早くヴィヴァルディ・ブームに火をつけ、「四季」を流行らせた最大の功労者である。日本でも何度演奏したことだろう。第1楽章「春」の軽快なリズムが流れた時に、よそのアンサンブルとは1味も2味も違うメッセージが届けられたような気がした。さすがに本家本元、響きの1つ1つが溌剌として、最終楽章「冬」まで、流れるような運びである。ヴァイオリン・ソロを弾いたコンサートマスターのアントニオ・サルヴァトーレと合奏団の呼吸もぴたりと合い、無窮の小宇宙が眼前に出現した。その他、モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」でみせた弦の甘美なブレンドが、心地よかった。(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |

|
「ナタリー・デセイ オペラ・アリア・コンサート」11月15日 オペラシティコンサートホール 驚異のコロラトゥーラ・ソプラノとして、世界の劇場を席巻しているナタリー・デセイ。2度目の来日となる今回も、2004年の初来日時と同様、オペラの序曲とアリアで構成されたコンサートで日本の聴衆の前に登場した。歌われたアリアは、この秋、メトロポリタン・オペラのシーズンオープニングで絶賛を博したドニゼッティの「ランメルモールのルチア」から2曲と、ヴェルディの「シチリア島の夕べの祈り」「椿姫」から各々1曲。 デセイの強みは、持って生まれた高い声域と完璧なテクニック、そして「声」も含めた演技力にある。3年前よりいっそう深みと奥行きが加わり、中声域も含めてふくらみを増した声は、ルチアの少女性から、「椿姫」の女性性までを幅広く表現。会場を興奮の渦に巻き込んだ。アンコールで歌われた「マノン」のアリア「ガヴォット」は、声の色合いを自在に操って圧巻。スターの存在感を見せつけられた公演だった。エヴェリーノ・ピドの指揮はやや単調の感も。オーケストラは東京フィルハーモニー管弦楽団。(加藤 浩子) 〈Photo: Shannon Higgins〉 |
| Classic CONCERT Review | |

|
「ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団」来日公演 旧東独の古都ドレスデンに本拠を構えるドレスデン国立歌劇場は、16世紀にさかのぼる歴史と、ヨーロッパ屈指の水準を誇る名門歌劇場である。オーケストラもきわめてレベルが高いが、そのオーケストラの精鋭で構成される「ドレスデン歌劇場室内管弦楽団」が来日公演を行うことになった。古楽奏法にも造詣が深いヘルムート・ブラニーの指揮のもと、バロックと古典派を得意とする楽団だが、今回はヴィヴァルディの「四季」、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」といったおなじみの名曲に加え、脳こうそくから復帰、「左手のピアニスト」として活躍する舘野泉をソリストに迎え、吉松隆のピアノ協奏曲「ケフェウス・ノート」が初演される(12月10日)。地方公演では人気ソプラノ歌手、森麻季との共演も予定。盛りだくさんの公演になりそうだ。問い合わせ先 ジャパン・アーツ( 03-5237-7711) http://japanarts.co.jp/ (K) |
| Classic INFORMATION | |

|
「メラニー・ホリデイ&ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラ」1月13日午後3時フェスティバルホール 「ニューイヤー・コンサート」といえば、まずメラニーの名前が浮かぶほどである。かつてオペレッタの殿堂ウィーン・フォルクスオーパーのプリマとして君臨し、絶大な人気を誇った。歌ってよし、踊ってよし、そして容姿は抜群。まさに3拍子そろったスターである。オーケストラはシェーンブルン宮殿の定期演奏会に出演し、数々の海外公演で実績を積んできた。おなじみのワルツやポルカはもちろん、ミュージカルのヒットナンバーもそろえて、楽しく、華やかな舞台づくりを目指す。料金は4,000〜9,000円。 お問い合わせはフェスティバルホール(06−6231−2221)へ。(T) |
| Classic INFORMATION | |

|
「エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団《ヨハネ受難曲》」 復活祭を目前に控えた3月ごろは、受難曲の季節。来2008年は、2月から3月にかけて海外からも3団体(聖トーマス教会合唱団、オランダ・バッハ協会、エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団)が来日し、「ヨハネ」「マタイ」のバッハの2大受難曲を競演する。このうち刺激的な公演になりそうなのが、イギリス古楽界の精鋭で構成されている「エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団」による「ヨハネ受難曲」(2008年3月2日、東京オペラシティコンサートホール)。今回の上演の特徴は、指揮者を置かず、エヴァンゲリストを歌うテノールのマーク・パドモアがリーダーとなることだろう。かねてから指揮者なしでバッハの受難曲を演奏したいと考えていたというエンライトメント管弦楽団とパドモアは、2005年以来このポリシーで共演し、「《ヨハネ受難曲》の世界を掘り下げた」と絶賛されている。他のソリストも、マイケル・チャンス、キャロリン・サンプソンら国際的なスターが揃った。 問い合わせ=東京オペラシティ(03-5353-0770) http://www.operacity.jp/ (K) 〈Photo: Marco Borgrewe〉 |
| Audio ALBUM Review | |
| 「G.カサド:無伴奏チェロ組曲/チェロ:藤村俊介」(MEISTER/MM-1214) カタルーニャの生んだ20世紀のチェリスト・作曲家であるガスパール・カサドの手になる「無伴奏チェロ組曲」とJ.S.バッハの「無伴奏チェロ組曲」から1番、3番をカップリングした魅力的なディスクである。奏者の藤村俊介氏はNHK交響楽団のフォアシュピーラーを務め、チェロカルテット≪ラ・クァルティーナ≫のメンバーである。武蔵野音楽大学シューベルトホールでのワンポイントステレオ録音でハードディスクからダイレクトカッティングされた。43歳と若いのに華麗さを狙わず、堅実な人柄を伝える優しく緩急を慈しむ安定した演奏である。藤村氏の練習場でしばしば音楽会の催される鎌倉市二階堂のイーゲルホールでの演奏と比較して聴いてみたいと思った。(大橋 伸太郎) |
|
| Audio ALBUM Review | |
| 「MARIA/チェチーリア・バルトーリ」(DECCA/475 9078)*輸入盤 筆者のポリシーとして製品評価で聴く試聴盤には、実際の公演を聴いたアーティストのディスクを使うことにしている。録音は生演奏では条件が違うが、演奏(声)の芯は一つだからである。ところがCDは沢山持っているに何故かステージに縁のないアーティストがいて、メゾソプラノの圧倒的第一人者チェチーリア・バルトーリがそう。オペラもリサイタルもすべて聞き逃している。そのバルトーリが、オペラの歴史に名を留めるメゾソプラノ歌手、マリア・マリブラン(1808〜1836)に捧げた新録音がこれである。19世紀半ばに28歳で世を去ったマリアの声を誰も偲ぶ由はないが、バルトーリは持ち前の光を撒き散らすような声で私たちを時間を超えた音楽体験へ誘う。(大橋 伸太郎) |
|