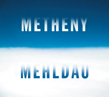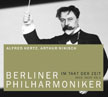![]()
| Popular ALBUM Review | |
| 「ザ・ロード・トゥ・エスコンディード/J.J.ケイル&エリック・クラプトン」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPCR-12495) 黒人ブルースマンへの憧れと並んでクラプトンを衝き動かしつづけてきたものに、ブルースを吸収したうえで独自の音楽を創造する力を持った同世代の白人アーティストへの嫉妬がある。「コケイン」や「アフター・ミッドナイト」の作者であり、謎の多いライフ・スタイルでも知られるJ.J.ケイルはその筆頭。こうしてついに実現した二人のジョイン作でクラプトンは、大半をケイルの曲で埋め、彼の名前を先にクレジットするなど、その思い入れをこれでもかというほどに表現している。ツアーにも参加しているドイル・ブラムホールIIとデレク・トラックス、近年交流を深めているジョン・メイヤー、そして故ビリー・プレストンら、バック陣のプレイも素晴らしい。(大友 博) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「グレイト・ロック・クラシックス/ロッド・ステュワート」 (BMG JAPAN/BVCM-31201) 昔の名曲を歌うのが大はやりだ。ジャズ・ヴォーカルの流行とも呼応している部分もあるが、60〜70年代の曲を歌い直すものも数多い。過去を振り返るのは後ろ向きなのか?というと、ブルース・スプリングスティーンのピート・シーガー物のように現代に強いメッセージを送ってくるものもあるが、概して懐古的だ。スタンダード物で当ててきたロッドが8年ぶりでロックを歌った新作も、往年の名曲集で、極めて懐古的。いい選曲でシンプル&ポップなバックで歌っている彼は、原曲の意味や熱を省き、只々気持ちよ〜い。そこがまたヒットに繋がる?! バリー・マニロウの50年代物同様、クライヴ・デイヴィスの作戦は当たるに違いない。(鈴木 道子) 着こなしてスタンダード・ナンバーを歌うのもいいが(ちょっと出し過ぎたと思うけど)、やっぱり、ジーパンはいてロック・ナンバーを歌うのが一番しっくり来る。オープニングの「雨を見たかい」のハマり具合には驚いた(CCRの曲ってどのタイプもロッドに似合いそう♪)。これはイケるという確信が。エルヴィン・ビショップの「愛に狂って」(!)、原題にもなっているボブ・シーガーの「スティル・ザ・セイム」(シーガー盤は邦題が「裏切りのゲーム」)など‘いいとこ突いて来る’のが嬉しい限り。かつて‘女ロッド’といわれたボニー・タイラーの「イッツ・ア・ハートエイク」はこちらが本家盤かも(!?)。バッドフィンガーの「デイ・アフター・デイ」が微笑ましい♪ (上柴 とおる) |
|
| Popular ALBUM Review | |
|
「ホワッツ・ゴーイング・オン/ダーティ・ダズン・ブラス・バンド」 |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ラスカル・フラッツ/ラスカル・フラッツ」(エイベックス/CTCW-53089) 発売された4枚のアルバムがすべて200万枚を超えるセールスを上げ、近作2枚はビルボード初登場No.1に輝く等、全米で大人気のポップ・カントリー3人組が遂に日本でもお目見え。これは2000年発売のデビュー作だが聞き物は何といっても「アイム・ムーヴィン・オン」。彼らが単なるアイドルではないことを認識させる深遠なバラードで、人気の決定打となった。他の3枚(CTCW-53090〜92)を順に聞いていけば、その音楽的成長が実感できることだろう。美しいメロディとヴォーカル・ハーモニーが特徴で、70〜80年代ポップスの良質な部分を融合させたそのサウンドは、カントリーに免疫のない音楽ファンにもすんなりと受け入れられるはず。(森井 嘉浩) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ウォーク・ウィズ・ミー /ジャメリア」(東芝EMI/TOCP6622) UKブラック・ミュージック界を代表するMOBO賞を何度か受賞しているシンガー/ソングライター、ジャメリア。この第3作はR&B、ヒップホップの領域を越えて大きくロック、ポップへも踏み込んで、多彩なスタイルとサウンドの面白さが楽しめるものにしている。冒頭から期待を持たせ、中東風の趣を加えたアフリカ・バンバータとのコラボによる「ドゥ・ミー・ライト」はじめ、伸びのあるポップなストラングラース、ディペッシュ・モードのエレクトロニックスを思い切ってサンプリングした「ビウェア・オブ・ザ・ドッグ」など切り口もなかなかの出来。歌もしなやかで、曲によって表情を変え、愛らしくもダイナミックになるのもいい。(鈴木 道子) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「シーズンズ・オブ・ライフ/ジャニータ」(ビクターエンタテインメント/VICJ-61385) ディペッシュ・モードの「エンジョイ・ザ・サイレンス」をカヴァーし、これがこの夏アメリカのスムース・ジャズ・ステーションで大きな話題を呼んだジャニータ。母国フィンランドでは10代でスターの座を手にするが、その後NYに移住、このアルバムが3作目となる。基本テイストはジャズとボッサをブレンドした雰囲気たっぷりのアダルト・コンテンポラリー。よく練られた楽曲が連なりアッという間にアルバムを聴き終えてしまう。昨今 のメッセージする女性SSW系とはひと味違う緻密なサウンドがなんとも心地好い。(中田 利樹) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ホーム・フォー・クリスマス/ダリル・ホール&ジョン・オーツ」 (ビクターエンタテインメント/VICP-63630) 単発で「ジングル・ベル・ロック」(今回新録音で収録)を出したことはあったけど本格的なクリスマス・アルバムはこれが初めて♪メル・トーメの「ザ・クリスマス・ソング」や「オー・ホリー・ナイト」といったスタンダードな曲だけではなく、彼らの手になるオリジナル2曲が聞き物で「ノー・チャイルド・シュッド・エヴァー・クライ・オン・クリスマス」には思わず身震い!70年代の素敵なスウィート・ソウルを聞く思い。タイトル曲(新曲)も彼らにしか出せない味わい。これだからホール&オーツはやめられない♪‘ブルー・アイド・ソウル’な彼らの持ち味がふんだんに生かされたこのXマス盤は今後、シーズンの定番となるに違いない。(上柴 とおる) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ライヴ・イン・メリーランド’79/ニュー・バーバリアンズ」(MSI/MSIG0316〜7) ストーンズのロニー・ウッドが設立した新レーベル≪ウッデン≫第1弾と登場したのがニュー・バーバリアンズのライヴ音源。ロニーが中心となって1979年から80年初頭まで活動させたNBには、キース・リチャーズはじめイアン・マクレガン、ボビー・キーズ、スタンリー・クラーク、ジョセフ・ジギー・モデリスが参加(80年1月のライン・アップはすこし変更された)。今回2枚組CDとして79年5月5日のメリーランド州ラーゴ/キャピトル・センター・アリーナでのコンサートの模様がファンの前に登場したのだ。初のオフィシャル化、快挙!ストーンズ・ファン、マストの作品集である。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「巡る季節の中で/ザ・バーズ」(ソニーミュージック/MHCP-1199〜1203) アメリカン・ロックの‘開祖’ともいうべきザ・バーズのボックス・セットが出るのは1990年以来16年ぶりだが今回は同じく4枚組に加えて(新たな未発表音源も発掘されるなど選曲も仕切り直し)DVD(当時の映像)が1枚付加されており曲数も90曲から99曲へと増え、そして新規のリマスター音源を使用。バーズとしてデビューする以前のジェット・セット〜ビフィーターズ名義での楽曲に始まり、再結成時の音源もまじえて1964年〜1990年に至るまでの彼らの軌跡を辿ることが出来る充実の内容で、彼らを聞き育ったトム・ペティらのコメントも掲載されたブックレットを見ながら堪能したい。それにしてもこのボックスに邦題が付けられたのには唸った。(上柴 とおる) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ライヴ・アット・ザ・BBC/フリー」(ユニバーサルミュージック/UOCY1364〜5) 「フォーエヴァー/フリー」(ユニバーサルミュージック/UIBO-1106〜7)*DVD ポール・ロジャース、ポール・コゾフ、アンディ・フレイザー、サイモン・カークの4人で1968年に結成されたフリー、伝説のブリテッシュ・ロック・バンドとしてその存在は今でも多くのファンに語り継がれている。そんな彼らのBBCライヴ音源が2枚組CDでリリース。そして、DVDの方ではTVパフォーマンス、ワイト島フェスティバルの模様のほか今年夏のオリジナル・メンバー4人のインタビューも収録。短期間ながらも「オール・ライト・ナウ」ほかのヒットを放ち、素晴らしい活動をした彼らの魅力を改めてこの両作品で堪能できる。71年の初来日ライヴ/神田共立講堂&大手町サンケイホールを想い出す・・。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「サンクチュアリー/セレスティアム」(ソニーミュージック/MHCP-1148) ミレニウム、サジタリアスを手掛けたプロデューサーとしてソフト・ロック・ファンや熱心なビーチ・ボーイズ・フリークから高い評価を受けたゲイリー・アッシャー。その彼が1984年に発表したプロジェクトがこのセレスティアムだ。唯一となるアルバムがソフト・ロック紙ジャケ・リイシューの1枚として世界初CD化されたが、音的にはシンセサイザーを中心とした80'sならではのエレクトリック・ポップ。ただし、全編のリード・ヴォーカルを元フールズ・ゴールドのトム・ケリーが担当し、むしろAOR的な質感が前面に出ている。ローラ・ブラニガン他がカヴァーしたタイトル・チューンは今なお十分な存在感を提示してくれる。(中田 利樹) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「タイムレス・ラヴ/スモーキー・ロビンソン」 (ユニバーサルミュージック/UCCU-1138) 本年度≪JVCジャズ・フェスティバル・イン・ニューヨーク≫最大の呼び物はスモーキー・ロビンソンの出演であった。なぜスモーキーがジャズ祭に?と僕は不思議に感じたものだが、なるほど、本作の前哨戦だったわけだ。コンポーザーとしても数多くの名曲を残すスモーキーだが、このアルバムではスタンダード・ナンバーを歌うことに専念している。滑らかなアレンジ、無駄をそぎ落としたサウンドに乗った彼のヴォーカルは、まさしく絹の肌触り。幾多のシンガーに歌われてきた歴史あるメロディを、スモーキーならではの節回しで、とことんメロディアスに表現していく。豊穣な“うた”の世界に、強く感じ入った。(原田 和典) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ブルー/ダイアナ・ロス」(ユニバーサルミュージック/UCCU-1139) ダイアナ・ロスとジャズの結びつきは、なんといっても映画『ビリー・ホリデイ物語』に集約される。本アルバムはその直後にレコーディングされていたにもかかわらず、35年間も倉庫に眠っていた。フェイクを抑え、スキャットも控え、メロディや歌詞をシンプルに、だけど奥深く表現する若きダイアナ・ロス。シャバダバとかドゥビドゥリャとわめいているだけのジャズ・ヴォーカリストはこれを聴いて足元を見つめてはいかがか。ベニー・ゴルソンやオリヴァー・ネルソンなど一流ジャズメンが関与したアレンジも絶品。スプリームズや「アイム・カミング・アウト」ではわからなかったダイアナの魅力に浸れる。発売されて本当に良かった。(原田 和典) |
|
| Popular ALBUM Review | |
|
「メセニー・メルドー/パット・メセニー+ブッラド・メルドー」 |
|
| Popular ALBUM Review | |
|
「トゥギャザー・アゲイン/カーリン・クローグ&スティーブ・キューン」 |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「トワイライト/Saya」(ポニー・キャニオン/PCCY-60005) サンフランシスコ在住の美人ピアニスト、Sayaの6作目に当たる最新作。元“ネヴィル・ブラザーズ”のピアニストだったSayaはフェンダー・ローズの名手だが、本作では生ピアノしか弾いていない。シンプルなトリオ編成で、ジョー・サンプルの『虹の楽園』を彷彿とさせる美しいピアノと実に心地好いグルーブが楽しめる作品である。スティービー・ワンダー「Lately」「Isn’t She Lovely」、スティング「Fields Of Gold」、ジョニ・ミッチェル「Both Sides Now」など多彩なナンバーを演奏している。またSayaの優れたオリジナルも3曲収録されているが、特にタイトル曲のが、秀逸で文字通り「夕暮れ時」の情景が目に浮かんでくるようだ。元気を出したいときやドライヴのときに聴くと最高に気持ちいい!(高木 信哉) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「Groovin’ High/矢野沙織」 (コロムビアミュージックエンタテインメント/COCB53576) この新作は9重奏による小オーケストラ・サウンドからカルテットの演奏まで、ヴァラエティに富んだ編成になっており、アメリカのベテラン中心のトップ・ミュージシャンとの共演で、矢野沙織もまた一歩新しい世界に踏み出した。ジェイムス・ムーディ、ランディ・ブレッカー、スライド・ハンプトンらと共演し、「マンテカ」「グルービン・ハイ」「ビリーズ・バウンス」などバップ曲でも生き生きとしたプレイを聴かせ、好調である。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ア・フランクション・オブ・ユー/フレドリカ・スタール」 (BMG JAPAN/BVCJ-31045) パリ在住のシンガー、フレドリカ・スタールの颯爽たるデビュー作。フレドリカは、スウェーデン生まれのまだ22歳で、高校を卒業した後、ミュージシャンになろうと単身フランスに渡った。やがてピアニストのトム・マククラングに才能を認められ、デビューのチャンスを掴んだ。昨年9月、パリの名門ジャズ・クラブ“ニュー・モーニング”で、初ライブを行い、一躍注目の存在となる。歌の上手さに思わず聞き惚れるが、ピアノとギターも演奏出来る。さらに驚くのが収録された全曲が彼女の作詞・作曲によるオリジナルであることだ!センスが良く、優れた詩が書ける。フレドリカは、ロバータ・ガンバリーニやソフィー・ミルマンに次ぐ才能溢れる大型新人だ。(高木 信哉) |
|
| Popular ALBUM Review | |
 |
「ゴー・ストレイト・トゥLA/福井ともみ」(Bassline Music Ltd/BLM-425266J) ジャズのライヴ・ハウスで大活躍中のピアニスト、福井ともみによるファースト・アルバム。切れ味のいいスインギーなプレイは刺戟的で溌剌としていて、しかもさわやかだ。スタン・ギルバート(b)、ラルフ・ペンランド(ds)という名手が共演したLA録音で、彼女の力強い打鍵は彼らを向こうに廻して堂々たるプレイをみせる。ちょっとモーダルな「オー・バロッキー」「ジー・ベイビー・エイント・グッド・トゥ・ユー」など佳演ぞろいだ。(岩浪 洋三) |
| Popular DVD Review | |
| 「レット・ザ・グッド・タイムス・ロール/ビル・ワイマンズ・リズム・キングス」 (ワーナーミュージック・ジャパン/WPBR-90594) ローリング・ストーンズを脱退してからビル・ワイマンが自らのロックンロールのルーツを探るユニットとして携わってきたのがリズム・キングス。そのリズム・キングスのツアーの様子を本公演とライヴ・ハイライトの二部、そしてツアー・ドキュメンタリーとでまとめたのがこのDVD。ライヴのちょっと変則的な二部構成的編集はおそらくこのツアーでのレパートリーがここで全曲聴けるという趣旨の配慮なのだろうし、ファン思いなところと彼ら自身のこの音楽へかけた愛情がよく伝わってくる作品だ。メンバーも錚々たる顔触れなのでドキュメンタリーもおもしろい。個人的にアルバート・リーが長く話している映像を初めて観られて嬉しかった。(高見 展) |
|
| Popular DVD Review | |
| 「BEST OF THE BEATLES ビートルズ誕生秘話 ピート・ベスト物語/ピート・ベスト」(ビクターエンタテインメント/VIBY-5055) ビートルズがレコード・デビューするまでの2年間(1960年8月から62年8月)にわたってドラマーを務めたピート・ベストに焦点をあてたデビュー前ビートルズのドキュメンタリー作品。デビュー後のハンブルク公演でのカラー映像が初公開されているほか、ブリティッシュ・インヴェージョン当時にピートが母親のモナ・ベストと共にアメリカのテレビ番組に出演した時の貴重な映像も含まれている。シンシア・レノン、アストリット・キルヒヘル、クラウス・フォアマン、ケン・タウンゼンド、ノーマン・スミスら、ビートルズの成功を後押しした人々の貴重な証言もたっぷり収録。NHK放送時にはカットされた30分の映像も含め120分の完全版としてDVD化された。(広田 寛治) |
|
| Popular BOOK Review | |
  |
「The Rolling Stone OUT OF THEIR HEADS Photos 1965-67/1982・Gered Mankowitz」(Schwarzkopf & Schwarzkopf)イギリス版 ローリング・ストーンズのオフィシャル・フォトグラファーのみならず、『アウト・オブ・アワー・ヘッズ』などのジャケット写真も手掛け、ある意味で60年代中盤のストーンズの最も知られているイメージを写真として形にしたギャレット・マンコウィッツのあまりにも豪華な写真集が敢行された。なにが嬉しいかといえば、大判であまりにも印刷がきれいなところ。上下巻構成からもわかる通り、ふんだんに写真が収録されていて、60年代期のストーンズの歩みを息遣いと感じ取ることができる。そうした意味で興味深いのは上巻後半から下巻前半へかけてバンドがアメリカを体験していくところ。まさに「サティスファクション」の誕生の瞬間なのだ。(高見 展) *一般書店では取り扱っていません 定価:\53000 送料:\2000 購入希望者は、住所/氏名/電話番号、そして≪OUT OF THEIR HEADS≫を明記して下記までE-メールをお願いします。 info@we-want-stones.com |
| Popular BOOK Review | |
| 「世界最高のジャズ/原田和典」(光文社) 入門者向けに書いたというが、十分に著者の個性と主張、好みも込められていて、とても刺戟的な一冊でもある。本書が中心になっているのは、ジャズ史に偉大な足跡を残してきたビッグ・スターのプロフィールと著者の聴き方だが、ルイ・アームストロング、デューク・エリントンにはじまり、マイルス・デイビス、オーネット・コールマン、ウェイン・ショーターに至る人選も納得がいく。エピソードも豊富に挿入されており、読み物としても楽しいし、自己の体験が織り込まれているのもいい。(岩浪 洋三) |
|
| Popular BOOK Review | |
| 「ロカビリー/監修・鈴木カツ」(シンコーミュージック・エンタテイメント) 1950年代中期に産声をあげたアメリカン・ロックンロールは世界中の若者から歓迎され、その流れは脈々と現在の音楽文化のメインストリームとして受け継がれている。そのルーツこそロカビリーだ。ザ・キング、エルヴィス・プレスリーをはじめとした多くのミュージシャンが生み出していったロカビリーの魅力を500枚以上のアルバムからしっかりと教えてくれるのが本書。基本からネオ・ロカビリー、ブラック・ロカビリー、ガレージ・パンク・ロカビリー・・。そして、ヒルビリー・バップ/ウエスタン・スゥイングについても触れられているのだ。往年のマニアからロックンロール・キッズまでの幅広い音楽愛好家にお薦めする。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular CONCERT Review | |
 |
「ミルバ with ジョン・健・ヌッツォ」9月20日 Bunkamuraオーチャードホール ヨーロッパのスーパースター、ミルバが日系イタリア人のオペラ歌手ジョン・健・ヌッツォをゲストに迎え、15回目の来日を果たした。ミルバの美声は60代半ばとなっても衰えず、途中、伊/英/日語を交えながらのおしゃべりで親しみ深く、かつ充実感のあるものだった。従来ならメロディーを聴かせるミルバの美声だけが耳に残るのだが、今回はピアフの名曲やカンツォーネはじめヨーロッパの有名曲を芯に、曲の中に分け入っての表現もあり、年齢に呼応した深みが感じられた。ヌッツォは若い美声のテノールはいいなあ、と「誰も寝てはならない」ほかオペラの定番に聞き惚れたが、『ウェスト・サイド物語』の「マリア」にはガッカリ。初々しい恋の情熱など皆無でただ歌うだけ。こんな底の浅い「マリア」は初めてだ。美声に頼らず精進して欲しいと思う。が、「オー・ソレ・ミオ」始めデュエットもよく、楽しい一夕ではあった。(鈴木 道子) Photo by 岡村 啓嗣 |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「ガル・コスタ」9月22日 Blue Note TOKYO 15年ほど前に見て、品が良い上に、なんとスケールの大きいシンガーなのだろうと思った。オリジナル曲をバリバリ歌っていた。音楽することの楽しみにあふれた雰囲気は今もまったく変わっていないが、演目はガラリと替わり、この日はブラジリアン・ソング・ブックというべきステージであった。親交のあったアントニオ・カルロス・ジョビン、ミルトン・ナシメント、ルイス・ボンファ等の曲を、英語のMCを挟みながら、歌い上げるガル。個人的には耳タコ気味の曲が続いたが、それがガルの声や節回しで表現されると、文句なしに新鮮で、改めて作曲家たちと、ブラジルの地に敬意を示したくなる。だけど彼女の持ち歌も聴きたかった・・・。(原田 和典) 写真撮影:山路ゆか 取材協力:ブルーノート東京 |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「突然段ボール」9月23日 高円寺・無力無善寺 1977年に蔦木栄一・俊二兄弟が中心となって結成されたユニット。僕の中ではものすごく偉大なひとたちである。03年に栄一を失ったが、昨秋、新作『お尋ね者』を発表し、女性3人組“おにんこ!”をそのまま含む6人編成で活動している。かつては栄一が天才と狂気の間をさまようごときヴォーカルを聴かせたが、今の突段は俊二のコクのあるギターとヴォーカルが演奏をリードする。この日は「前後左右に動く」「シベリアパン」「猫殺しマギー」などを披露。徹底的にポップなのだけど、どうしようもなくよじれた世界を堪能させてくれた。来年は結成30周年。世界に誇るべき個性派集団が今後、どんな手に出るか。今からわくわくする。(原田 和典) |
| Popular INFORMATION | |
 |
「サム・ムーア〜プレミアム・ソウル・レジェンド・ナイツ〜」Blue Note Tokyo 1960年代中期から後半にかけて「ホールド・オン」「ぼくのベイビーに何か?」「ソウル・マン」「アイ・サンキュー」を大ヒットさせたダブル・ダイナマイト、サム&デイヴ。ソウルメン・オーケストラを率いてのその迫力あるソウルフルなステージが69年春に日本初のソウル・レビューとして実現。そんな伝説のR&B歌手、サム・ムーアが現シーンを代表するアーティストとのコラボレーションによる素晴らしい作品集「オーバーナイト・センセーション」をこの秋に発表した。往年のファンから若いR&Bキッズまで大きな注目を集めている中、急遽、御大のサム・ムーア来日が決定したのだ。見逃せないステージになることだろう。ライド・オン! *Blue Note Tokyo *11月13日(月)〜11月17日 各日午後8時からの1回公演 *ミュージック・チャージ:¥13,650(税込) http://www.bluenote.co.jp/ |
| Classic ALBUM Review | |
| 「ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲、ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番/カテリーナ・マヌーキアン」(ビクターエンタテインメント/VICC-60536) マヌーキアンは81年トロント生まれ。父はアルメニア人、母は日本人。94年カナダ音楽コンクール優勝以来、演奏活動を続けている。故ドロシー・ディレイに師事。現在、トロント大学の博士課程で哲学を学んでいる。当盤は、ショスタコーヴィチ生誕100年を記念して録音されたヴァイオリン協奏曲第1番と、アルメニアの作曲家ハチャトゥリアンのヴァイオリン協奏曲を併収。引き締まった音と安定した技巧が魅力。ショスタコーヴィチは強い意志を反映した推進力と感情の持続力を感じさせる熱演。ハチャトゥリアンはアルメニアの民族色を表出しながら真摯に弾きこんでいる。E.トプチアン指揮アルメニア・フィルハーモニー管弦楽団も出色の出来。(横堀 朱美) |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「ユーシア・クァルテット/シャコンヌと枯葉」(ユニバーサル ミュージック〈N&F〉/NF-63101) ユーシア・クァルテットの名称は、ヨーロッパとアジアの合成語で、高木和弘、ヤンネ舘野、小倉幸子、アドリアン・ズィトゥンの4人が結成した団体である。いま注目の長岡京室内アンサンブルのメンバーで、そのリーダー森悠子の門下生たちである。彼らは既に2001年に全米フィショフ室内楽コンクールで優勝した栄誉に輝き、完全に融合した音色と奏法で、弦楽四重奏の世界に新しい境地をひらいた。収録されたパーセル、ブリテン、武満徹の作品を聴けば、そのことがだれにも理解されるだろう。結成後まだ日が浅いにもかかわらず、もはや熟達の名演が展開されている。そこに彼らの抜群の才能を発見することで、新鮮な感動を覚えることになろう。(小石 忠男) |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「ラビリンス/スティング」(ユニバーサル ミュージック/UCCH-1018) スティング3年ぶりの新作は、「20年に渡って徐々にとりつかれていった」という、エリザベス王朝期の英国で活躍したリュート奏者兼作曲家ダウランドのリュート歌曲を歌った意欲作。当盤を聴き、「ダウランドの名曲をフォーク調で歌っているのに仰天した」と評した人もいたが、スティングの音楽をポリスの時代から聴き続けてきた人たちには、21世紀の吟遊詩人が17世紀のポップ・ソングに取り組んだことに、歴史的必然を感じるに違いない。スティングによれば「ダウランドはシンガー・ソングライターの先駆け」とのことで、エディン・カラマーゾフのリュート伴奏で歌うのみならず、格調高く物憂げで甘美な旋律をリュートで自ら奏し、手紙の朗読も交えるなど、選曲、構成、演奏、朗唱ともに興味深い1枚。(横堀 朱美〉 |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「心の翼/ポール・マッカートニー」(東芝EMI/TOCP70099) 8年ぶり4作目となるポールのクラシック・アルバム。オックスフォード大学モードリン・カレッジからの依頼でポールが作曲。ビートルズ時代に体験した嵐の夜のできごとから着想を得たという4楽章のオラトリオで、合唱とオーケストラをフィーチャーしたメロディアスな大作に仕上がっている。2006年3月にポール立ち会いのもとアビイ・ロード・スタジオで、ギャヴィン・グリーナウェイ指揮、キングス・カレッジ少年合唱団やアカデミー室内管弦楽団などにより録音された。(広田 寛治) ポール・マッカートニーにとって4作目となるクラシック・アルバム。オックスフォード大学モードリン・カレッジに新しいコンサートホールができたことを記念して、「ヘンデルの『メサイア』のような、世界中の人々に歌われる合唱曲を」と委嘱されたポールが、妻リンダの死の悲しみに暮れるなかで、8年の歳月をかけて作りあげた大作。『メサイア』のような本来の意味での宗教曲ではないけれど、ポール自身の個人的かつスピリチュアルな魂の告白と表現への天才的な創造性が結実した作品となっている。尊厳と優しさにみちた美しい旋律は聴く人を魅了してやまず、またメ悲しみから光へモを希求する人々の大きな力となってくれることだろう。(横堀 朱美) |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「ベートーヴェン、シューベルト、ハイドン:弦楽四重奏曲/タカーチ弦楽四重奏団」(ユニバーサル ミュージック/UCBD-1044) タカーチ弦楽四重奏団の演奏はダイナミックスと濃淡が明確で躍動感に溢れている。多くの優れたハンガリー系クァルテットの中でも一際目立つ存在と言える。1975年に結成され2年の間にエヴィアンとポーツマスの室内楽有名コンクールを制覇し、世界の楽壇に登場してきた逸材クァルテットである。曲はハイドンの「鳥」、シューベルトの「死と乙女」、ベートーヴェンの「ラズモフスキー第1」の3曲で特にベートーヴェンが素晴らしい。各曲の演奏前に演奏解釈等についてのレクチャーがあり、別チャプターでは4人の少年時代の環境など興味ある話を聞くことが出来る。(廣兼 正明) |
|
| Classic CONCERT Review | |
 |
「サイトウ・キネン・フェスティバル「サイトウ・キネン・オーケストラ/指揮:アラン・ギルバート」9月1日 長野県松本文化会館 アラン・ギルバートは豪腕の持ち主とみたい。自らの目指す方向にオーケストラをぐいぐい引っ張っていく。その持ち味が遺憾なく発揮されたのはマーラー「交響曲第5番」である。最初にトランペットが奏でる悲壮なファンファーレから、怒涛の逆巻くようなフィナーレまで、息を継がせる間もないほど緊迫感にあふれている。感傷的な楽章では抒情性にあふれ、官能的ですらある。ヒルボリ「Exquisite Corpse」はガラリと表情を変え、エンジンがフル回転して、疾走する。ここまでくると爽快としか言いようがない。武満徹「弦楽のためのレクイエム」には秘めやかな情感が流れていた。腕達者なソリストたちをそろえたオーケストラは、ロマン派から現代曲まで自由自在にこなし、優秀な機能性を改めて証明した。〈写真:ほそがや博信〉(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「サイトウ・キネン・フェスティバル 「メンデルスゾーン・オラトリオ〈エリア〉/指揮:小沢征爾」9月2日 まつもと市民芸術館 サイトウ・キネンは今年も賑わい、すっかり松本の「夏の風物詩」になった感がある。小沢はハイライトとなるメンデルスゾーンのオラトリオ「エリア」のタクトをとり、病後を思わせない健在ぶりを発揮した。 旧約聖書をもとに作曲されたロマン派屈指のオラトリオである。異教徒と戦い、苦闘の末に勝利を得た預言者エリアを主人公に、神への篤い信仰と熱烈な布教が、ドラマティックに描かれている。名バリトンのジョゼ・ヴァン・ダムが豊かな声量でエリアを演じ、敵と対決して奇跡を呼び起こす場面は圧巻といっていい。コントラルトのナターリー・シュトゥッツマンの声は伸びやかで艶があり、天使の役柄にふさわしい気品を備えている。慈雨が大地をうるおして神を称える群衆の大合唱は、終曲を迎えて最高潮に達した。東京オペラシンガーズの健闘が光る。 フィレンツェ歌劇場との共同制作で、ジャン・カルマンが演出を担当した。オペラさながらの舞台づくりで、メンデルスゾーンの本質に迫り、バロック期オラトリオとは異なる新しい方向を示唆した。〈写真:ほそがや博信〉(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「フィレンツェ歌劇場〈ファルスタッフ〉/指揮:ズビン・メータ」9月16日 東京文化会館 老騎士ファルスタッフは好色漢で悪事にも手を染めながら、どこか善良なところがあり、ころころ太った姿には愛嬌がある。この相反する性格の人物をジョルジョ・スリアンは年季の入ったバリトンで聴かせた。ユーモラスな仕草は絶品ながら、敵役としてのアクの強さにやや欠ける。ファルスタッフに妻を狙われるフォード役のマニュエル・ランツァは今が旬のテノールで、張りのある歌声で舞台を支えた。フォード夫人バルバラ・フリットリは絶妙の歌いぶりでソプラノの魅力を遺憾なく発揮、ナンネッタを演じたステファニア・ボンファデッリのリリック・ソプラノは明るく、軽やか。ファルスタッフを懲らしめる女声の奮闘が、この喜劇のもう一つの主役であることを浮き彫りにした。 ズビン・メータの熟達した指揮はオーケストラを伸びやかに歌わせ、歌手たちの好演を生み出した。このミュンヘン歌劇場のシェフはオペラの隅々まで知り尽くし、出演者を意のままに動かす術を身につけている。ルカ・ロンコーニの演出は抽象世界を克服して、現代的なリアリズムの美学を構築しつつある。〈写真:長谷川清徳〉(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「古典音楽協会 第135回定期演奏会 〜 同い年でもこんなにちがう〈バッハとヘンデル〉」9月28日 東京文化会館小ホール 古典音楽協会は1953年に創立され、53年の歴史があり、すでに100回を優に超えたプロの室内合奏団である。多くのファンに支えられ会場も満席だった。 今回は1685年という同じ年に生まれたバッハとヘンデルをとりあげ、全く異なった生活環境で音楽活動をした二人の人間像を抉り出した興味深い企画であった。 ヘンデルの「合奏協奏曲イ長調」はVn角道徹・新谷絵美、Vc藤沢俊樹の独奏で、明るく軽快だった。とりわけすばらしかったのは「チェンバロ協奏曲 変ロ長調」独奏佐藤征子だった。古典の繊細で優雅な響が印象的だった。バッハは対象的に暗く重く、それでいて「ブランデンブルク協奏曲第3番」に見られたように重厚で華麗な演奏が楽しめた。会場には全体に暖かい響がただよっていた。(斎藤 好司) |
| Classic INFORMATION | |
 |
「レニングラード国立歌劇場管弦楽団」12月2日午後2時 ザ・シンフォニーホール ロシアの名門オーケストラを率いて音楽監督のアンドレイ・アニハーノフが来日し、12月2日ザ・シンフォニーホール(06−6453−6000)で演奏会を開く。曲目はチャイコフスキー「交響曲第6番〈悲愴〉」、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、ボロディン歌劇「イーゴリ公」より<ダッタン人の踊り>。ピアニストには今人気のウラジミル・ミシュクを帯同し、若手の2人によりロシア音楽特集が組まれて、溌剌とした演奏が期待される。料金は1,000〜8,000円。(T) |