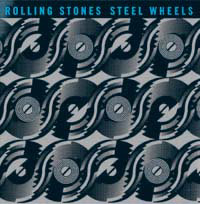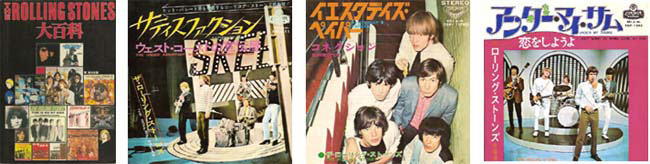|
中村 俊夫
『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』 (キングレコード/SLC-184) |
|
|
|
細川 真平
ジミ・ヘンドリックス「エレクトリック・レディランド」 |
|
|
|
町井 ハジメ
ザ・ローリング・ストーンズ『スティール・ホイールズ』 |
|
|


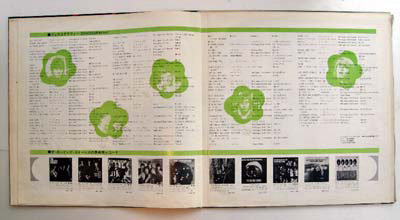 ここにとり上げた『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』は、当時ストーンズの日本発売権を持っていたキングレコードから67年12月にリリースされた日本企画コンピレーションで、『ミュージック・ライフ』誌と文化放送『ハロー・ポップス』における読者・聴取者投票で選ばれた上位12曲が収録された、まさに究極のベスト・アルバム。クリスマス・シーズンのレコード店頭で初めてこのアルバムを手にした私は、その12曲のラインアップに驚いた!
ここにとり上げた『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』は、当時ストーンズの日本発売権を持っていたキングレコードから67年12月にリリースされた日本企画コンピレーションで、『ミュージック・ライフ』誌と文化放送『ハロー・ポップス』における読者・聴取者投票で選ばれた上位12曲が収録された、まさに究極のベスト・アルバム。クリスマス・シーズンのレコード店頭で初めてこのアルバムを手にした私は、その12曲のラインアップに驚いた!